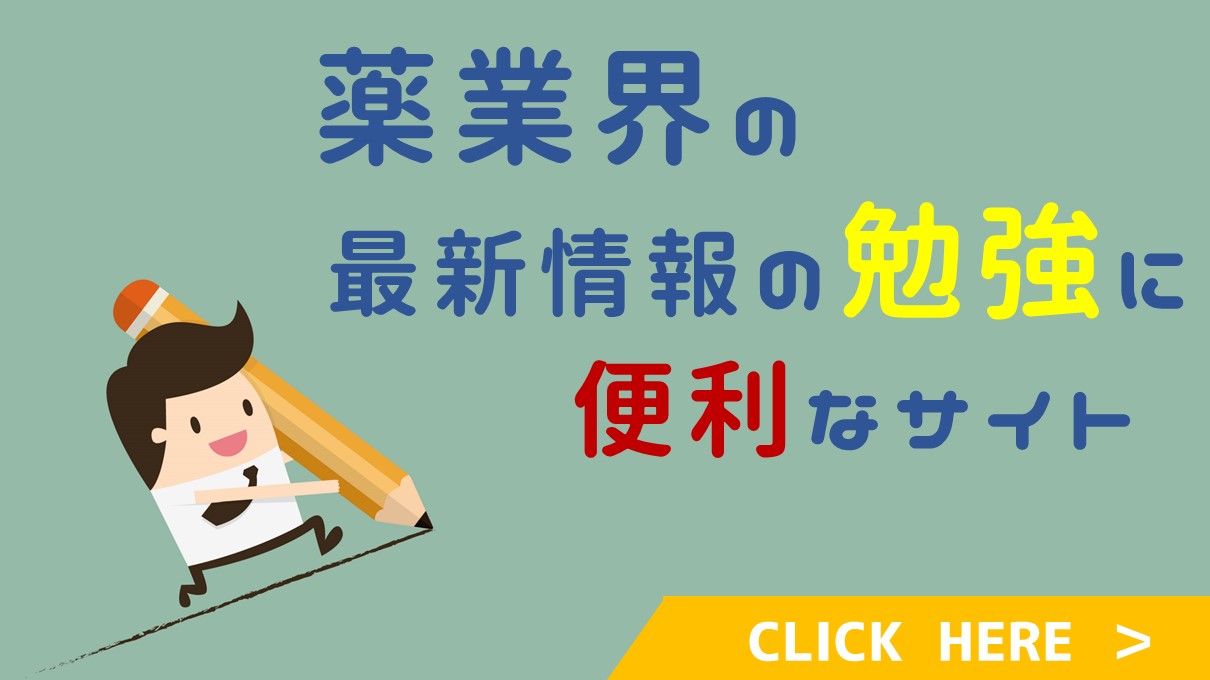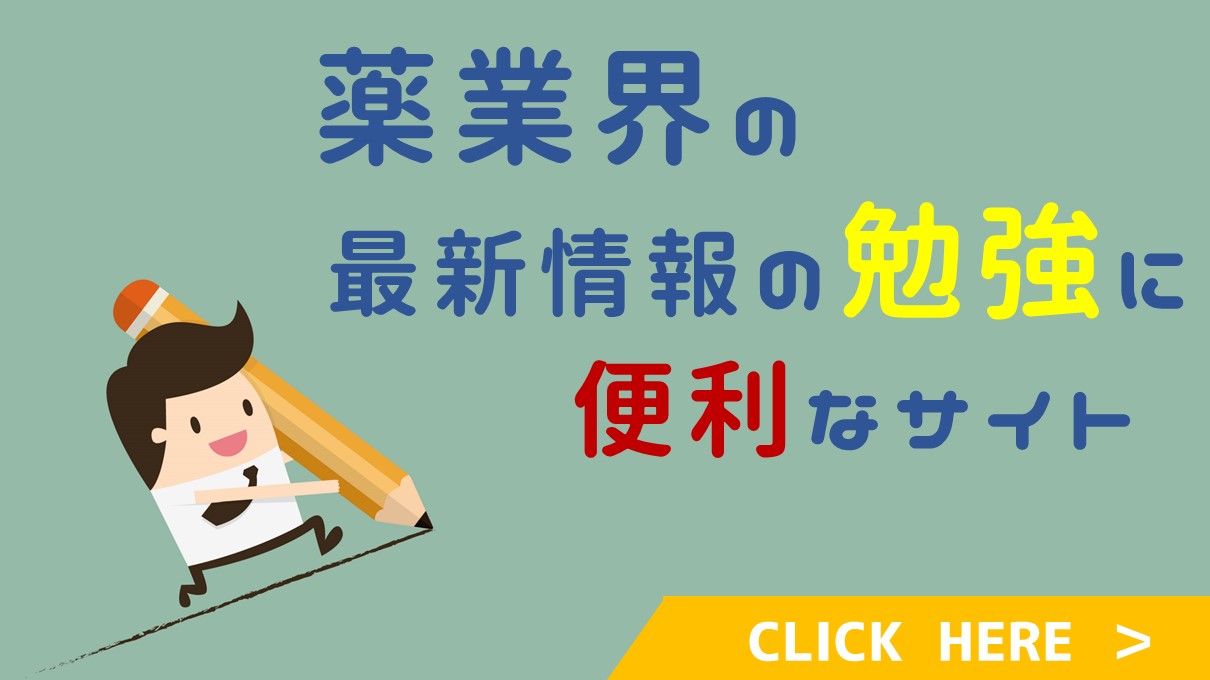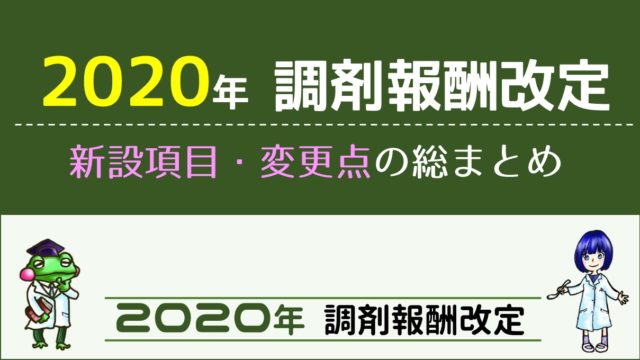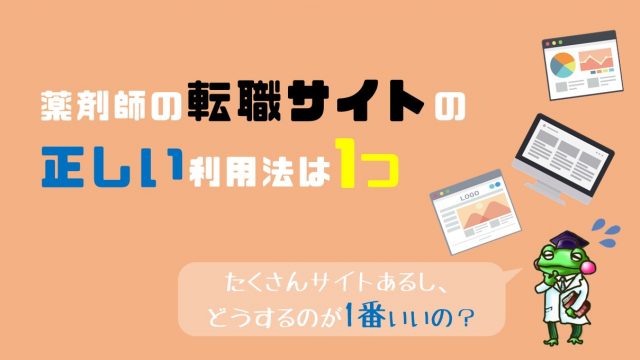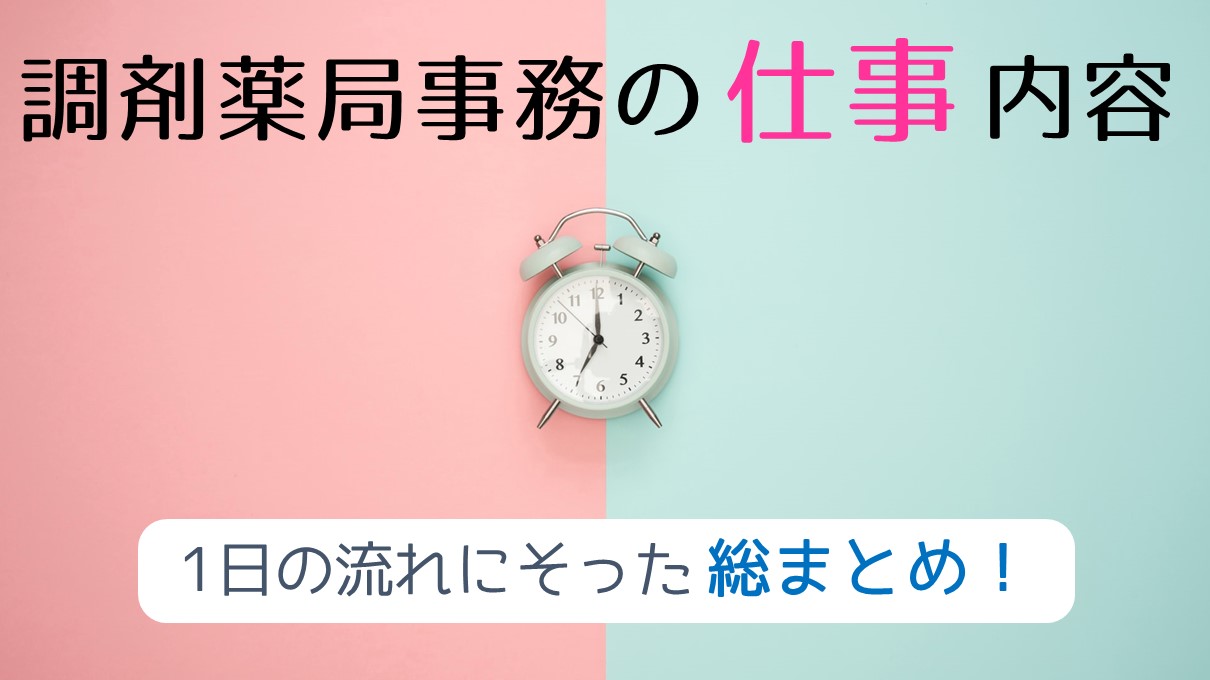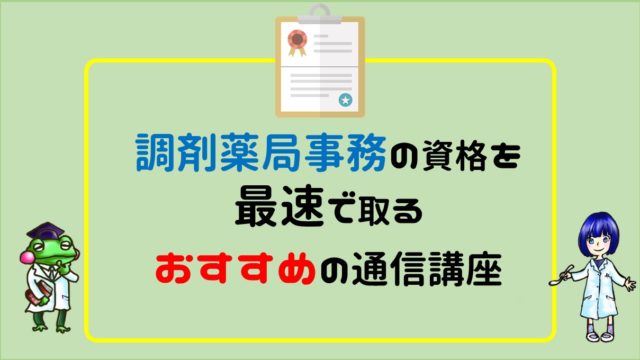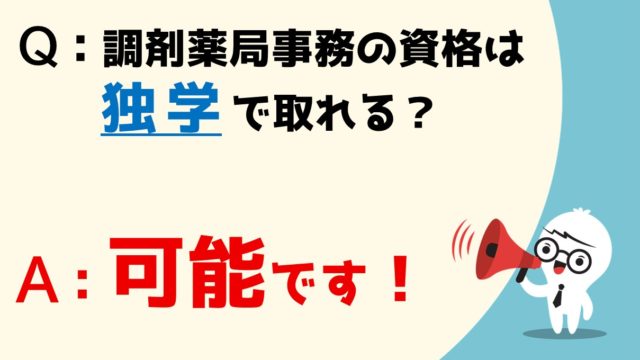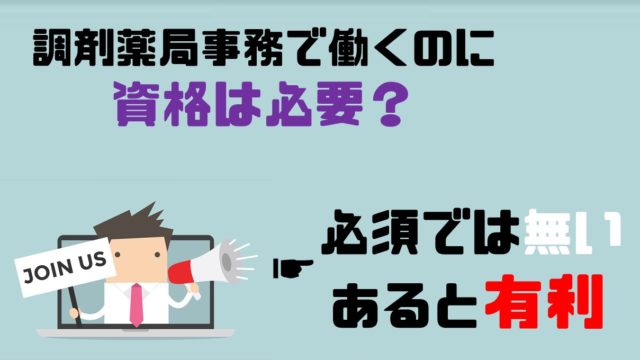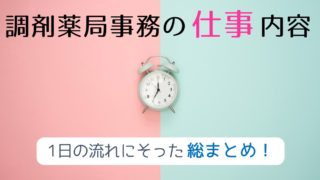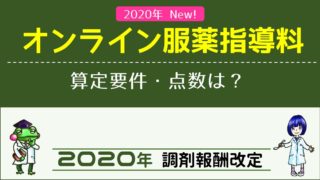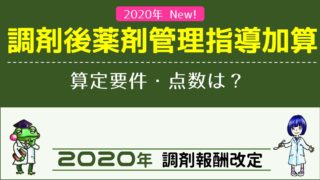薬局薬剤師のプジキです。
- 調剤薬局事務の業務内容を知りたい。
- 働きたいと考えているが、未経験なので仕事内容が分からなくて不安。
- 仕事が辛かったり大変ではないか気になる。
こういった悩みを解消すべく、薬局事務の業務内容をご紹介。
この記事を読んで貰えば、調剤事務の仕事にはどういった種類があるのか、全体像を知ることができます。
自分はいつも事務さんに仕事をお願いしている身なので、どんな仕事があるのしっかりと解説していきますね。
も く じ
調剤薬局事務の1日の流れ
イメージをつかむため、ざっくりと1日の流れを記載します。
- 9時出社~開店制服や白衣に着替えて開店準備。
- 11時患者対応患者さんから処方箋を受け取ってPCに入力。これがメインの仕事。また、接客をこなしつつ、薬剤師もフォロー。
- 13時お昼休憩スタッフとランチ休憩。お昼も開けるお店は順番にお昼を取る。
- 16時納品対応卸が薬を納品したら、内容の確認と棚への格納。店舗によっては1日に複数こなす。
- 18時閉店~帰社閉店したらレジ金のチェック。お店を閉める準備をし帰宅。
営業時間に関しては一般的に、朝の9時から開始して19時に閉店する薬局が多いです。
近くにある病院の営業時間と同じぐらいの営業時間にすることが通常なので、その病院が遅くまで営業してると薬局の営業も遅い時間となる。
お昼休みは13~14時になることが多いですけど、お昼も営業しているお店では、患者さんの込み具合によって柔軟に休み時間を取りますね。
残業は、基本的に少ない。営業時間を過ぎても患者さんが残っている場合は残業発生しますが、それ以外ではほとんど無いです。
薬剤師は残業することが多い店舗でも、事務さんは先に帰ることができます。というのも、だいたいが薬剤師しかできない仕事(法律上)で残業しているので、手伝ってもらうことができない。
なので、定時で帰れることが多い職種ですね。
さて、次の章からが、具体的に業務内容をみていきましょう!
開店業務から業務開始まで

出勤したら、まずはオープン準備。薬局が開店する前の短い時間で行う。
だいたい、10~15分ぐらいで準備していくので、サクサクっとこなしていきます
鍵を開けて薬局内へ
一番早く出勤すると、店舗の鍵を開けるところから開始です。
薬局では、警備システムを入れてる場合が多く、入口のドアを開けると警備システムが作動し、店舗全体にけたたましい音が鳴り響く。
これ、『1分以内に整備システムを解除しないと、警備会社に連絡がいく』という仕組みなので、店舗に入りしだいスピーディーにシステム解除する必要がある。
慣れない頃は、これがプレッシャーだったりするので、焦らずにシステムの解除をしましょう。
その後、出勤の記録をつけて持ち物をしまい、制服に着替えたらオープン準備を進めていきます。
パソコンなどシステムの立ち上げ
まずは、薬局のシステム関連の電源を付けてまわります。
薬局内では、パソコンはモチロンのこと、薬の作成に使用する機械(例えば、薬を小分けにする分包機)や、待合室の血圧測定器など、色んな機器を置いている。
システムが立ち上がるまで時間がかかるものもあるため、真っ先に機械のスイッチを入れる。
電話の設定解除
営業が終了すると、電話を転送や留守電に設定しているので、それを解除する。
これ、意外と忘れるポイントだったりする。
なんか電話鳴らないなぁーと思ってたら、「留守電の解除してなかったー!!」ってのはあるある。
うちの薬局では、転送設定を解除するまで電話機に付箋をつけておくことで、解除忘れを防いでますね。
薬局の清掃
続いて清掃。薬局の中も外も掃除します。
薬局の内側は、待合室と調剤室に分かれます。待合室が患者さんが待つところで、調剤室は薬を作る部屋ですね。
全体を掃除機がけして、椅子や机を水拭きする。棚に置いてある売り物だったり、配布資料もきれいに整える。
薬局の外側は、ゴミや落ち葉をきれいにする。街路樹とか公園が目の前にあると、10~11月ごろの落ち葉の量は半端なく、落ち葉を拾うだけでかなりの時間を取られる。。
薬局は清潔感が大事なので、ここはしっかりと行います。
看板やのぼりの準備
薬局の外に看板やのぼりを出してる店舗は、オープン準備のタイミングで外に設置します。
営業時間いがいは通行の邪魔になるので、看板などを薬局の中にしまっている。
これ、看板ものぼりの旗もけっこう重かったり、のぼりは長いので入口にひっかかったりと、準備するのが地味にやっかい。
朝礼会議
上記の準備が終わったら、最後に朝礼会議。業務連絡や、薬局に関連するニュースの共有、お休みしてる人の確認などを行う。
朝礼会議は、昼に実施したり夜に行うケースもある。また、個人が経営している薬局では、こういった会議じたい無いところが多い。
メインの日中業務


調剤薬局事務のメイン業務は、患者さんへの接客業務と、処方せんをレセコン(PC)へ入力する作業になります。
具体的にみていきましょう!
接客業務(受付)
患者さんが薬局に入店(来局)してきたら、基本的には事務さんに応対してもらいます。まさに薬局の顔ですね。
患者さんは、何らかしら健康に不安を抱えているから薬を貰っているので、ホスピタリティ精神をわすれず笑顔で対応しましょう。
患者さんから処方箋を預かり、保険証の確認をしたり、初めての来局であればアンケートの記入をお願いしたりする。
受付がおわったら、薬ができるまで待合室でお待ちいただくよう、促しましょう。
処方せんをレセコンへ入力
続いて、事務さんの最もメインの仕事、パソコンで処方せんを入力する作業。
「ん?パソコン?じゃあ、レセコンとは何?」という疑問を持つ人もいると思うので、ここの内容については少し詳しくまとめますね。
患者さんから処方せんを受け取ったら、書いてある内容をパソコンへと入力します。それには次の2つの意味がある。
- 患者さんへ渡す薬の説明書や袋に記載する内容を作成するため
- レセプト(調剤報酬明細書)を作成するため
①は具体的にどんなものかというと、薬局で薬を貰うときに薬の説明が書かれた紙や袋を貰いませんか?薬の飲み方とか、こんな効果がありますよとか、こんな副作用出るから注意してね、とか書いてあるやつ。アレを作成するためです。
②は、「レセプト請求」というもので使用するデータを作成するため。レセプトとは、患者さんに「今回請求する費用の明細はコレですよー」と見せるための明細書(調剤報酬明細書)のことを言う。※「レセプト請求」の業務については、後ほどコチラで解説します。
この「レセプト」を元に患者さんからお薬代を頂くので、薬局の経営に直結してくる大事な業務になります。
薬局のパソコンにはレセプトを作成するためのソフトが入っているので、「レセコン(レセプトコンピューター)」と呼ぶのです。
以上のように、2つの意味で大事なレセコンへの入力作業。レセコンの入力には慣れが必要で、経験量と知識が必須な業務です。
そのため、間違えずに、かつ、素早く入力できると、薬局では重宝されます。
調剤薬局事務の資格取得講座で、レセコンの使い方を同時で教えるものもあるぐらいで、レセコン入力のスキルが身についてると大変助かります。
公式調剤薬局事務+コンピューター講座セット【ヒューマンアカデミー】
(※リンク先の一番下)
■費用:39,000円
※上記は以下の記事で触れています。興味があれば併せて読んでみてください。
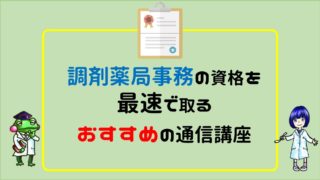
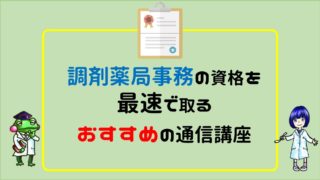
患者に渡す薬袋・薬情・領収書等を準備
レセコンへ処方せん情報の入力が完了すると、薬を入れる袋や薬の説明書などが印刷されます。
薬を入れる袋を『薬袋(やくたい)』、薬の説明書を『薬情(やくじょう)』といいます。
印刷された薬袋や薬情を、対象の患者さんの分として準備します。
事務さんが処方箋の入力や薬袋の準備をしている間に、薬剤師は患者さんの薬を用意しているので、準備ができたら薬剤師に渡してあげましょう。
お会計
薬剤師が患者さんにお薬を渡し終えたら、最後に会計をします。これを担当してもらう。
ちなみに会計は、その店舗のルールによって誰が担当するか異なる。薬局によっては薬剤師が薬を渡した後に会計まで行う場合もある。
ここで、お金の受け渡しを間違えると、最後のレジ締め(下の方で記載してます)で大変なことになるので、くれぐれも間違えないように注意が必要(汗
ピッキング(内服薬を取り揃える)
患者さんの薬を準備する作業は基本的に薬剤師が行いますが、それを一部事務さんが手伝う場合もあります。
法律上、薬を作成するすべての作業を行うことはできませんが、飲み薬のシートを集める作業(=「ピッキング」と言います)はOKです。
ちなみにちょっと豆知識で、、、事務さんに薬集めを手伝ってもらうという仕事は、昔からあったものの、実は薬局業界でグレーとされていました。
2019年4月2日に、厚生労働省(薬局を管轄してます)から正式に通知がでて、薬剤師の薬を集める業務の一部を薬局事務が補助して良いとなりました。
※4月2日に出た通知なので、通称「0402(ゼロヨンゼロニー)通知」なんて呼ばれてる。覚えておくと知っている人だと思われるので、ぜひ覚えておきましょう。
間違えずにすばやく準備するには、どこに何の薬が置いてあるのか把握せねばならず、最初のうちは覚えることがとても大変です。正直、薬剤師もかなり苦労します。
その他の日中業務


続いて、日中の所々で発生する業務についてまとめていきます。
こちらは、先ほど紹介したメイン業務の間に発生する業務になりますね。
薬の発注と納品の受け入れ
薬のストックが少なくなってきたら、医薬品の卸へ薬を発注をします。
昔は電話やFAXで発注してたけど、今はwebで発注するのが一般的。オンラインショッピング感覚ですね。
発注した薬は、卸が薬局へ直接運んで納品してくれる。
納品される医薬品が間違っていないか、納品伝票に照らし合わせながら確認をして、受け取ります。
薬の格納
受け取った医薬品を、薬を入れてある棚(『調剤棚』と呼ぶ)にしまいます。
調剤棚には、100種類以上の薬が置いてあるので、納品物をどこにしまうのか探すのも、慣れないと一苦労。
逆に、薬の場所を覚えてしまうと一瞬で終わります。
先ほど紹介した「ピッキング」の仕事をする前の準備として、医薬品の格納作業で薬の配置を覚えてもらったりします。
納品書や請求書など帳票の整理
薬の納品と一緒に届く納品書、卸からの請求書など、さまざまな所から届く帳票を整理して保管します。
これは、『会社法』という法律で、帳票の種類によって保存しなければならない期間があるためです。
きちんと整理しておかないと、いざという時に大変な思いをするので、受け取って帳票はすぐに片付けてしまいましょう。
不要になった処方せんの廃棄
処方せんも一定期間の保管が必要で、原則3年のあいだ保存しなければならない。その保管期間が過ぎたら廃棄します。
この処方せん、スーパー個人情報。取り扱いには細心の注意をはらう必要がある。
そのままゴミとして廃棄するのではなく、店内のシュレッダーで処理をしてから捨てる。
このシュレッダー作業、処方せんの枚数が多いお店では結構な時間を取られるので、空いた時間にコツコツとお願いしてます。
専門の廃棄業者へ委託してる薬局もあるけど、シュレッダーで廃棄してる店舗が多いイメージですね。
電話対応
店舗にかかってくる電話の受付をしてもらいます。
患者さんからかかってくることもあり、その場合は薬剤師へとバトンタッチしてもらう。
あと、薬剤師を狙った営業電話も多いため、うまく断ってもらったりします。
閉店業務


最後に、薬局の締め作業。これが終わったら、1日の業務が完了です。
売上金の集計
1日の売上が間違っていないか、レジのお金やクレジットカード、QR決済などキャッシュレス系の売り上げを確認していきます。
レセコン上の売り上げと、レジ金等をまとめた売上が同じ金額であれば作業完了。数分で終わります。
ただ、売り上げがずれていた時は大惨事。どの患者さんで金額がずれているのか、レシートを見ながら1件ずつ確認作業をしていく。
患者数が多ければ多いほど確認に時間がとられる。複数の患者さんで金額が間違っていた場合などは、めんどくさくて目も当てられなくなる。
会計ミスがおきてしまった患者さんを特定できた場合は、間違ってしまったことを連絡する。
連絡する内容としては、多く貰い過ぎていたので返金が必要な場合か、少なくいただいていたので足りない分の請求をお願いする場合のどちらか。
・・・お会計をミスると本当に大変なので、くれぐれも注意したい。
清掃
お店を開けるときにも掃除したけど、閉めるときにも掃除をします。朝と同じように調剤室と待合室をキレイにしていきましょう。
翌日の朝にもう一度清掃はしますけど、このタイミングでしっかりと片付けておかないと、翌日に時間がかかるはめになる。
特に調剤室は、薬の箱・袋のゴミが置きっぱなしになっていたり、粉薬が散らかっていたりするので、念入りに掃除します。
薬局たるもの、清潔感は大事ですからね。
PCなどのシステムの電源を消す
使い終わったシステム機器類の電源を落としていきます。点けっぱなしはエコじゃないですからね。
注意したいのは、電源を落としていく順番。レセコンは親機・子機と分かれていて、親機は最後に電源を落とす必要がある。
データのバックアップにも影響してくるので、くれぐれも注意して電源を落としていきましょう。
電話の設定
留守電または転送するため、電話の設定を変更します。
これをしないと、夜間に患者から連絡がきたとき対応できないので、必ずセットする。
看板やのぼりの撤収
店外に出していた看板やらを店内にしまいましょう。
雨が降っているときや風が強いときは汚れているので、しっかりと拭き取ってから店内にしまわないと、薬局内が汚れるので注意。
施錠して帰宅
後片付けが終わり、退勤の記録をしたら、薬局の入口に鍵を閉めて終わりです。
警備システムを入れている店舗ではセットしてから店舗に施錠するんですけど、「システムセットしてから●分以内に出ないと、警備会社へ連絡される」という仕組みになっている。
そのため、警備システムを入れる人と、ドアを押さえる人、ドアの鍵を閉める人、という具合にチームプレイが発揮される。
時々ある業務


最後は、毎日ではないけれど、ときどき発生する業務について紹介します。
レセプト請求業務
処方せんをレセコンに入力して作成したレセプト(さっきココで紹介したやつです)を元に、保険金の請求をする。通称、『レセプト請求業務』とよぶ。
「保険金の請求?レセプト請求??」のように、初めて聞く人にはよく分からないと思うので、何のことか簡単に説明しますね。
日本は『国民皆保険制度』といって、国民すべてが医療保険に加入している。
そのため、患者は医療費の3割を負担するだけで医療を受けることができる。残りの7割は国や保険者が負担をしている。
この、国などが負担している7割分については、決まった手順で「お金をくれー!」と請求しないと、支払われない。
この、7割分を請求することを『レセプト請求』と呼びます。
このレセプト請求というのは、1カ月のレセプト情報を翌月の10日までに処理しなければならない。例えば3月分のレセプトは4月10日までにレセプト請求するのだ。
このレセプト請求は、作業じたいは一瞬で終わる。
ただ、この作業を忘れたりすると、売り上げの7割に当たるお金を請求できないという、薬局の経営的にはとんでもない事態におちいる。
絶対に忘れないように注意したい仕事です。
棚卸し
薬局も小売りなので、棚卸を行います。
棚卸:店舗の商品数を数えて、在庫の金額を算出すること。
実施回数としては、だいたい年に2~4回行うのが多い。大手の薬局チェーンでは、毎月おこなっている所もある。
これ、小売りで仕事をしてて棚卸したことある人は分かると思いますが、、、商品の数が多ければ多いほど大変。
薬局では、取り扱っている薬の数は平均すると1,000種類ぐらいあるので、数えるのも一苦労。
棚卸の日はいつも、朝から気合を入れて臨んでます。
定期的なお勉強会
薬局では、薬のメーカーが主催する薬の勉強会が定期的に開かれる。主に薬剤師が対象だけど、うちの薬局では事務さんにも参加してもらってる。
この勉強会、メーカーさんが豪華なお弁当を提供してくれる。
久しぶりに参加したメーカさんの勉強会。金ピカの箱に詰められた銀座KYOKUの肉弁当、美味そうでたまらない。。。! pic.twitter.com/ogDiYGUSpN
— プジキ@ガチ頑張る薬剤師ブロガー (@pujiki) June 12, 2018
自分では買わない2~3千円ぐらいのお弁当をいただけるので、いつも大変美味しくいただいている。
立派なお弁当を楽しみつつ、薬に関する知識を深めてもらいます。
まとめ
調剤薬局事務の一般的な仕事内容として、やることがたくさんあるように映るかもしれません。
メインは事務作業と接客になりして、入社して3カ月も過ぎるころには、サクサクと仕事をこなせるようになってきます。
調剤薬局事務で働きたいと考えているひとは、ぜひ参考にしてみてください(و`ω´)و


【答え】継続的な勉強
2019年5月に厚労省が出した薬剤師の需要と供給についてのレポートをご存知ですか?
これ簡単に言うと『すでに薬剤師が余り出している』という内容が書いてある。需要を上回る数の薬剤師がいるそうだ。
突然ですが、最近の新卒の採用事情はご存知ですか?
調剤薬局やドラッグストアは、昔はそれこそ薬剤師の資格を持っていれば即採用というぐらい簡単でした。
でも今はちがう。優秀な成績の薬剤師に絞り始めていて、成績が悪い薬剤師は採用しない。
この流れが、じわじわと中途採用にも来ています。なぜそんなこと分かるかというと、これでも薬剤師の採用を担当してますから、動向はチェックしてるのです。
薬剤師が飽和していく未来に対し、すこしでも質を高めて需要の高い人材となるため、ぜひ日々の勉強に役立ててください(و`ω´)و