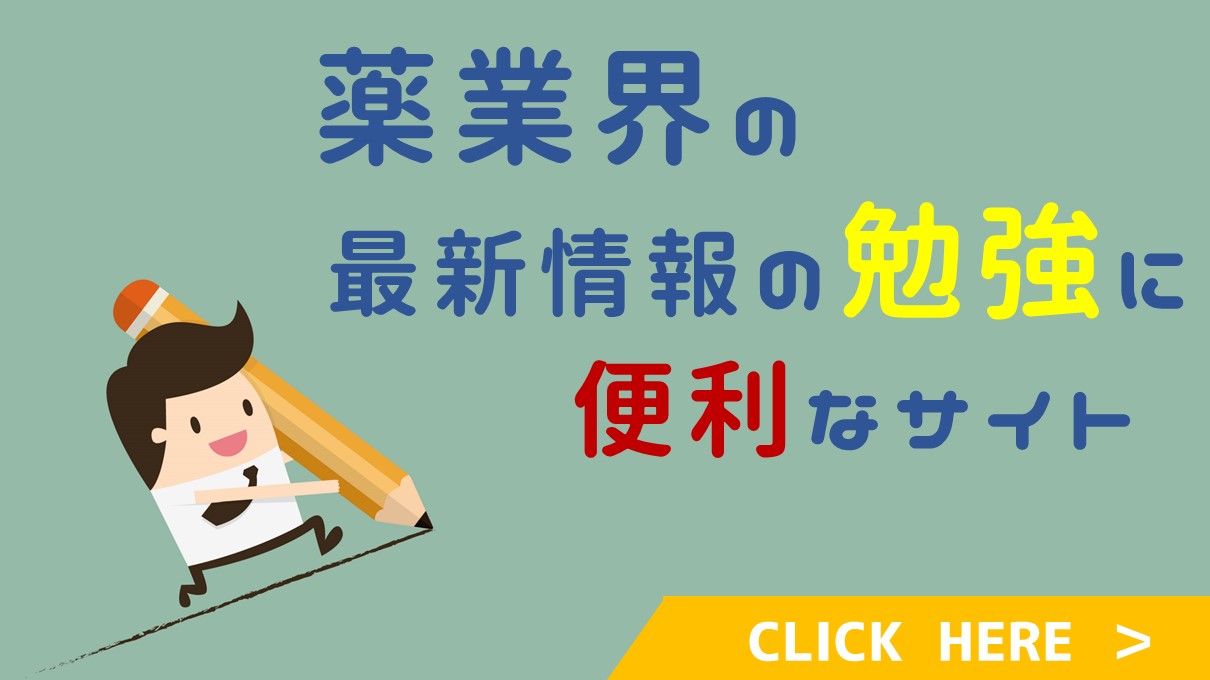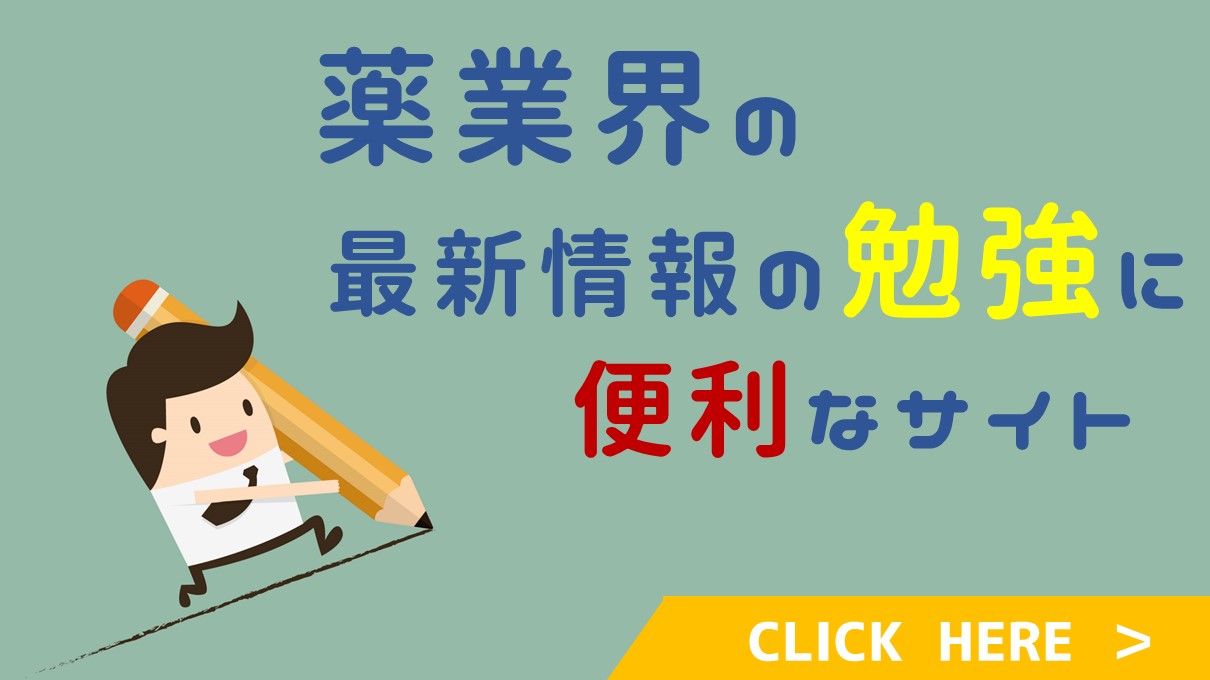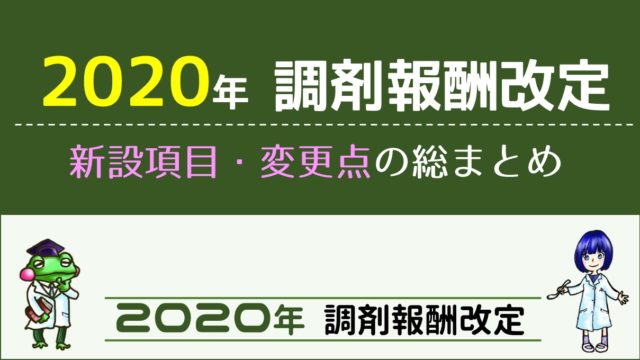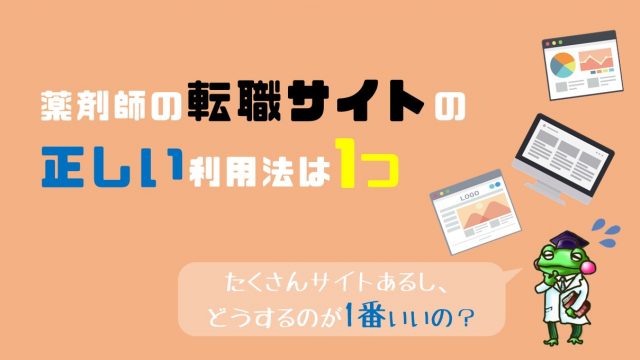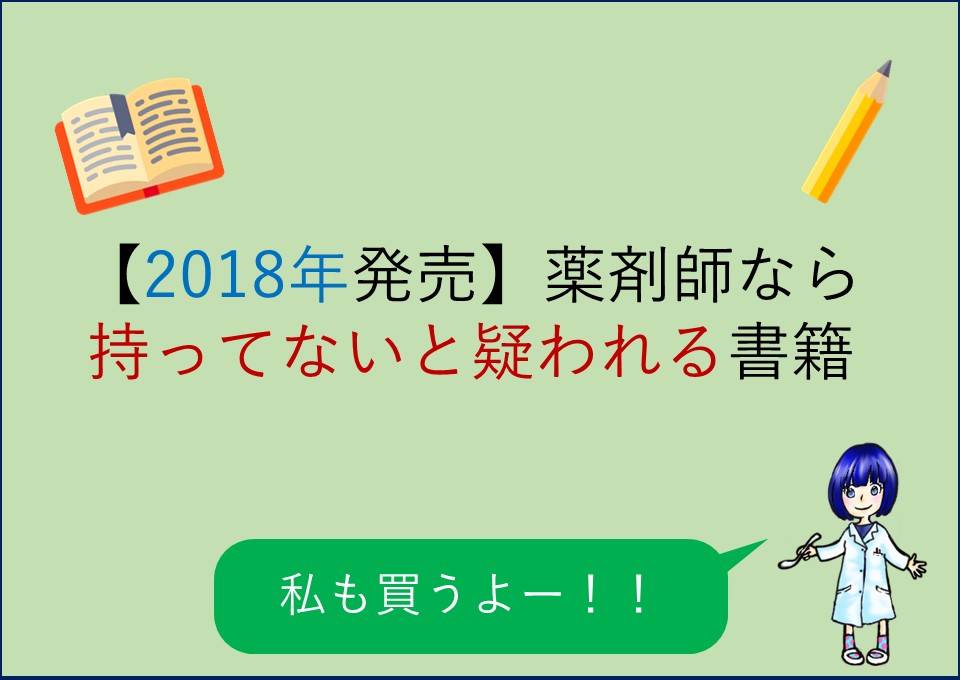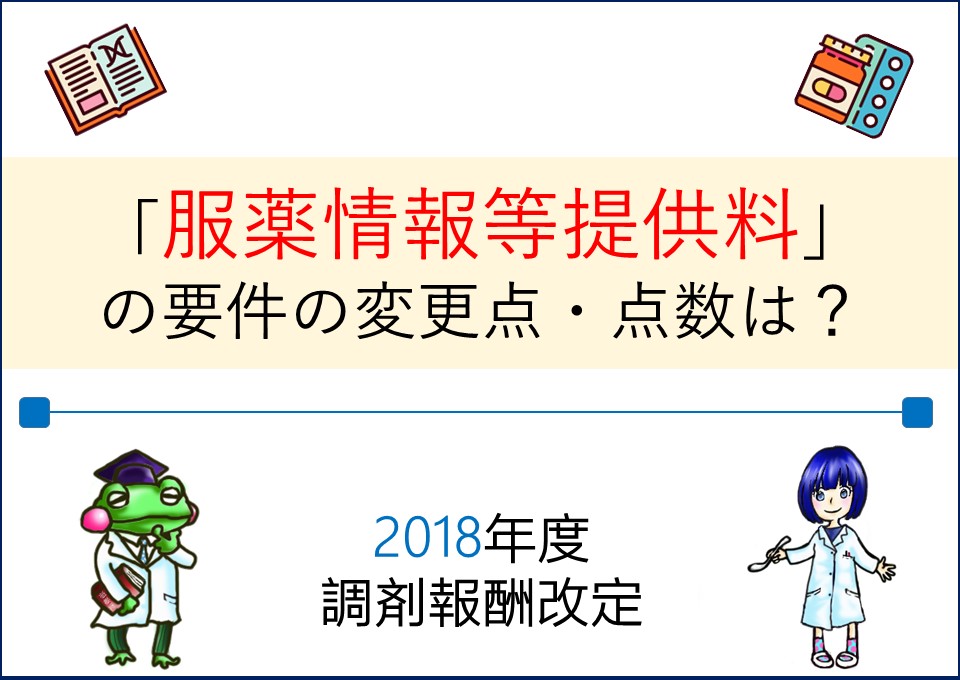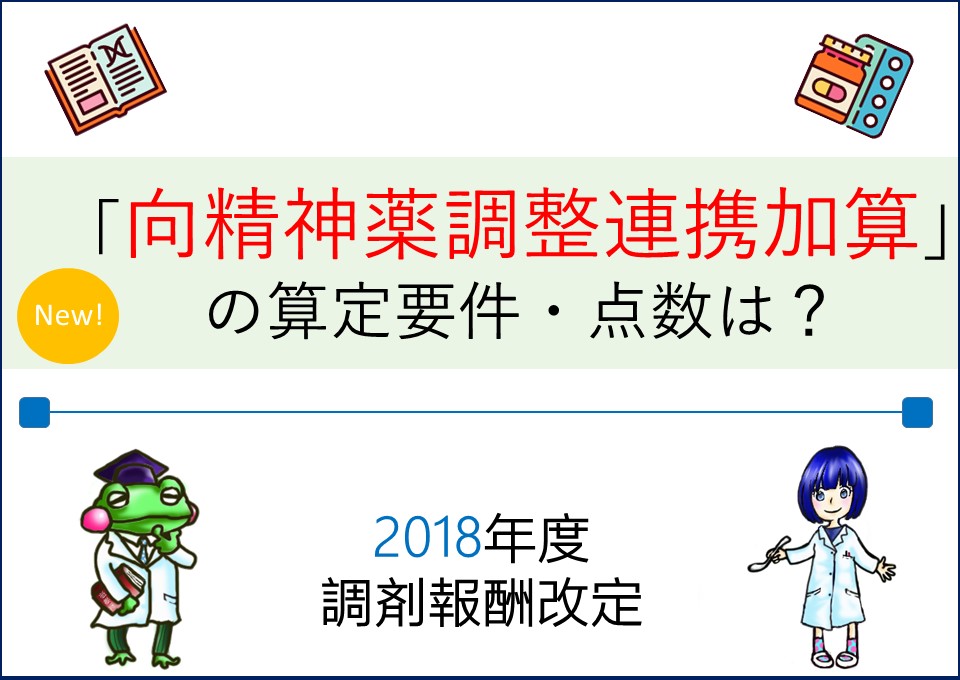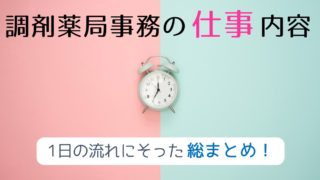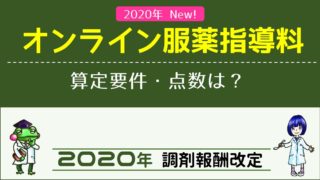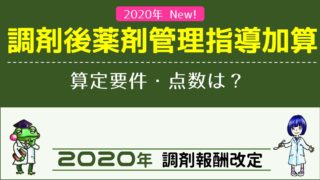この1月という時期は、薬局関係者(特に薬剤師)なら、絶対に買ったことのある書籍が発売される時期です。
ということで紹介します(自分の確認もかねて)
2018年に発売される書籍を書き殴る。 気づくと手首に巻いてある輪ゴムのような体の一部的な書籍から、「そんなのあったの!?」といったあまり知られていない含め、ちょっとだけ説明も添えて紹介する。
30秒もあれば読み終わるので、ぜひサッと目を通して、「そういえば、買わなきゃ!」なんていう本(今日の治療薬とかね!)がないか確認だけしてみて下さい。
も く じ
今日の治療薬2018
最初にご紹介するのは「今日の治療薬」。薬局界隈では、今日(コンニチ)と略される。
なぜ最初に紹介したかというと、買った(更新した)から。
薬効ごとに各医薬品が簡潔にまとめられた良書。 「分からないときの今日」として、新人薬剤師時代から愛用してる一冊。 病院の先生も、診察室に置いてあったりする(チャンスあれば見てみて)
今回から追加になったガイドライン(一部)が、疾病のスタンダードな治療をザっと見返すのに役立ちそう。
ちなみに毎年、表紙の色が変わります。豆知識。 2018年は黄色と、金運が高まりそう(笑)
[発売日:2018年1月10日]
今日の治療指針 2018年版[ポケット版]
この本は薬剤師向けというより、どちらかというと医師向けの本。なぜなら、治療方針とそれに対する薬物療法の注意点がまとめられた書籍だから。
でもだからこそ、薬剤師に読んでもらいたい!
「対物業務から対人業務へ!」と患者に対する投薬行為が重要視されてきている。 対人業務に深みを増すためには、「どんな処方意図でこの薬剤を処方しているのか?」の理解は必須。
ぶっちゃけ値段は高めだけど、処方薬に対する理解を深め、患者への投薬を一歩進んだものにするため、辞書として身近に置いて損はない本です。
[発売日:2018年1月10日]
治療薬マニュアル2018
といった会話が社交辞令的に繰り広げられる、薬剤師バイブルの双璧ともいえる治療薬マニュアル。 もう片方のバイブル(今日の治療薬)と比べ、病態の説明が詳しいことが特徴。
プジキは『薬局薬剤師=今日の治療薬』、『病院薬剤師=治療薬マニュアル』というイメージがあるけれど、最終的には個人の使いやすさで決めるのが一番ですね。
[発売日:2018年1月10日]
治療薬ハンドブック2018
治療薬マニュアルがコンパクトにまとまった感じの本。本を買うとアプリが使えて、添付文書の確認とか製剤写真をオフラインでも見れる。
在宅でちょっとした調べものをしたい時に、アプリを通して調べられるのは便利そう。ネットで十分かもしれないけど(汗
[発売日:2018年1月11日]
治療薬インデックス2018
一包化の注意点が「湿気」とか「冷所」などに分けて書いてあったりと、薬剤の特性がまとまった本。
日経DIでコラムも書いてる笹嶋勝さん監修。
[発売日:2017年12月15日]
こころの治療薬ハンドブック 第11版
抗精神薬がまとめられたハンドブック。
2018年は医師側の診療報酬に『向精神薬調整連携加算』という、向精神薬を減らすと加算が貰える要件が追加になり、薬剤師としても向精神薬の使い分けなど知識をつける需要は高くまりそう。
この機会に、一度買ってみようかと考え中の本。
[発売日:2018年1月31日]
ポケット医薬品集
こちらも医薬品の情報が要点を押さえてまとめられている良書。ポケット医薬品を好む薬剤師もけっこういる。
この本、『1,373ページ』もあるから、タイトルの通りポケット(白衣)に入れようとしても、「ぐにゃーん」って折れ曲がるので注意。
Pocket Drugs(ポケット・ドラッグス)2018
これ、、、自分も存在を知らなかった(汗 なので、書籍の紹介をそのまま記載します。。
治療薬を薬効ごとに分類し、第一線で活躍の臨床医による「臨床解説」、すぐに役立つ「選び方・使い方」、薬剤選択・使用の「エビデンス」を、コンパクトにまとめた。
欲しい情報がすぐに探せるフルカラー印刷で、主要な薬剤は製剤写真も掲載。臨床現場で本当に必要な情報だけをまとめた1冊。
2018年版では、運転注意・休薬・投与期間制限等の情報を追加し、コンパクトなサイズのまま、さらに充実。
[発売日:2018年1月10日]
まとめ
毎年更新するとお金が馬鹿にならないけど、新薬に対応ができなくなってくる。 ので、プジキは2~3年に一度ぐらいの間隔で更新してる。 なけなしのお小遣いで(泣
薬剤師にとってバイブルとも呼べる書籍なので、自己投資もかねて、ぜひチェックしてくださいー!
薬局に関する勉強に便利なサイト
最後に、私がブログを書くときの記事ネタを探したり、情報収集に活用しているサイトの『m3
m3は、薬局に関連性のある最新情報を国内外問わずにまとめて確認できるため、効率的に知識を補えるので助かっている。
一例ですけど、こういった情報が毎日更新される↓


こう、非常に興味をひかれるコンテンツが豊富。それで、毎日更新される。 なので、毎朝の通勤時間でサッと記事のタイトルだけ見ておけば、「え、知らないの?」といった取り残されるリスクが無くなる。※アプリがあるので便利。
閲覧するためには登録が必要なんだけど、お財布にやさしく登録費が無料。登録時に入力する内容は名前とか生年月日などで、「1分」あれば登録ができる。
なので、登録するか悩むぐらいなら、その悩んでる時間で登録完了する。
あと地味に嬉しいのは、サイト内の勉強動画を見ると『m3ポイント』なるものが貯まり、『Amazonギフト』と交換できる。情報収集しながらお小遣い稼ぎできるのが一石二鳥。
他の薬剤師向け情報サイトでは有料登録しないと読めないネタが、m3で掲載してることもあるので、登録して損は無いというか、「使わないのが損」な貴重なサイト。
すべての薬剤師に自信を持っておススメできるので、他の薬剤師に差をつけられる前にぜひ活用してみてください(و`ω´)و
公式サイトm3
【答え】継続的な勉強
2019年5月に厚労省が出した薬剤師の需要と供給についてのレポートをご存知ですか?
これ簡単に言うと『すでに薬剤師が余り出している』という内容が書いてある。需要を上回る数の薬剤師がいるそうだ。
突然ですが、最近の新卒の採用事情はご存知ですか?
調剤薬局やドラッグストアは、昔はそれこそ薬剤師の資格を持っていれば即採用というぐらい簡単でした。
でも今はちがう。優秀な成績の薬剤師に絞り始めていて、成績が悪い薬剤師は採用しない。
この流れが、じわじわと中途採用にも来ています。なぜそんなこと分かるかというと、これでも薬剤師の採用を担当してますから、動向はチェックしてるのです。
薬剤師が飽和していく未来に対し、すこしでも質を高めて需要の高い人材となるため、ぜひ日々の勉強に役立ててください(و`ω´)و