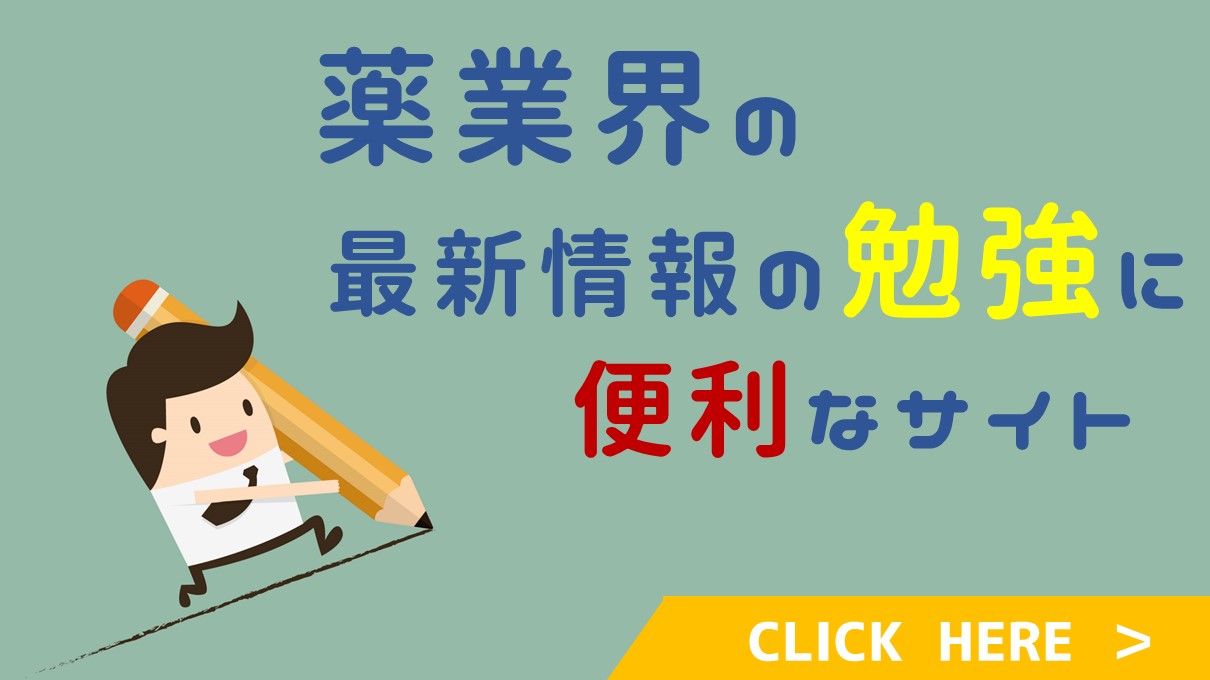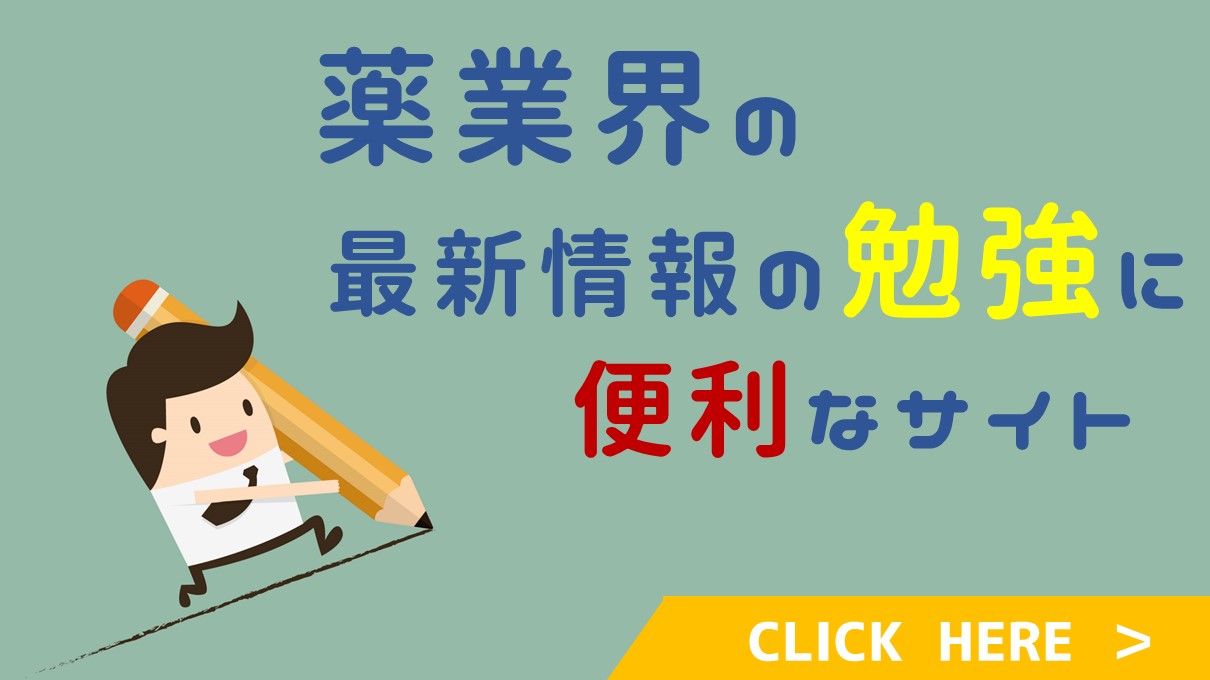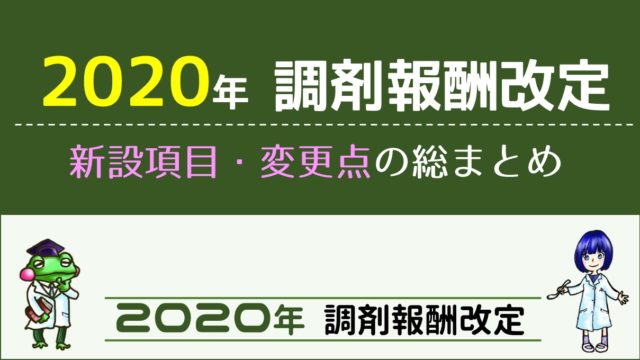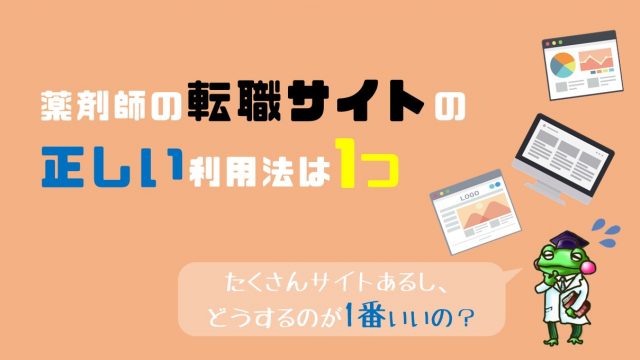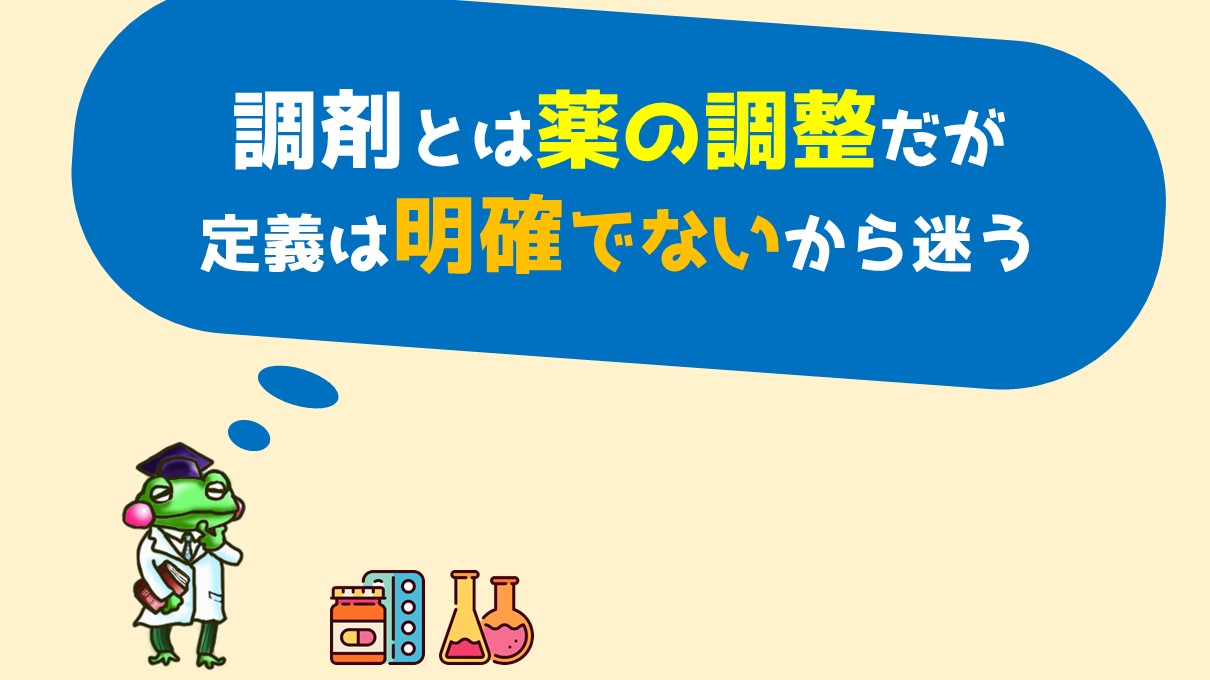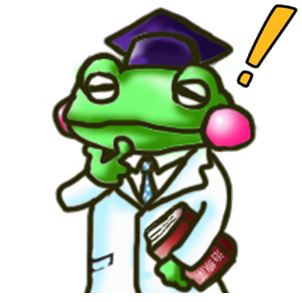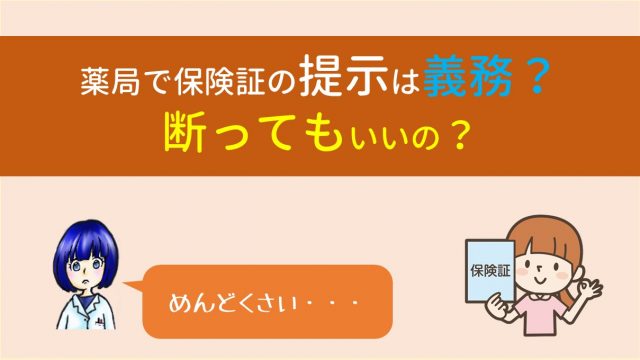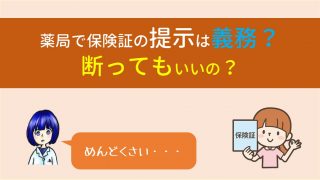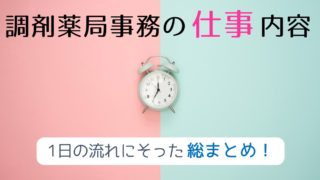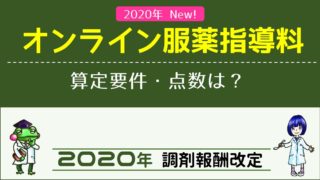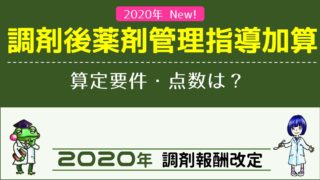チェーン薬局で教育担当をしている、現役薬剤師のプジキです。
といった疑問に、法律や国の方針ふまえて答えていく。まず初めに意味を簡単に説明すると(↓)
<狭い意味>
薬の調整。医師の処方せん通りに医薬品をそろえること。
<広い意味>
医師の処方内容が薬学的に正しいのか判断(処方監査)し、相互作用のチェック、患者への服薬指導とその内容の記録・管理、後発医薬品の選択など、医薬品に関わる多種多様な業務のすべて。
「なんで狭い意味と広い意味の2つあんねん!どう決まってんねん!」とツッコミたくなる気持ちになる人もいるでしょう。これは、法律からわかる側面と、国が薬剤師にもとめている仕事内容という側面の2つから、上記のような狭義・広義の2つの意味がでているのです。
も く じ
法律からみた『調剤』の定義とは?
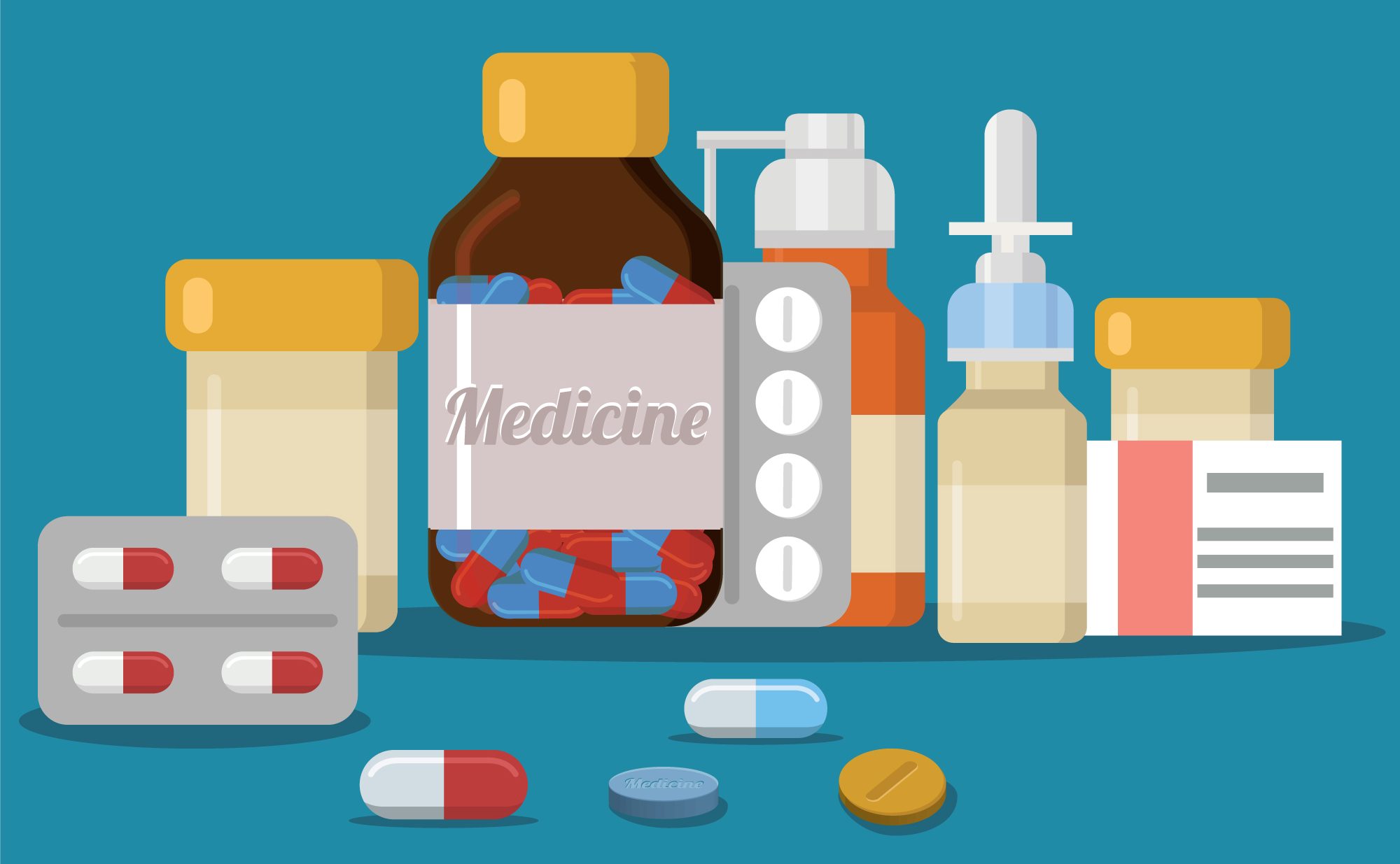
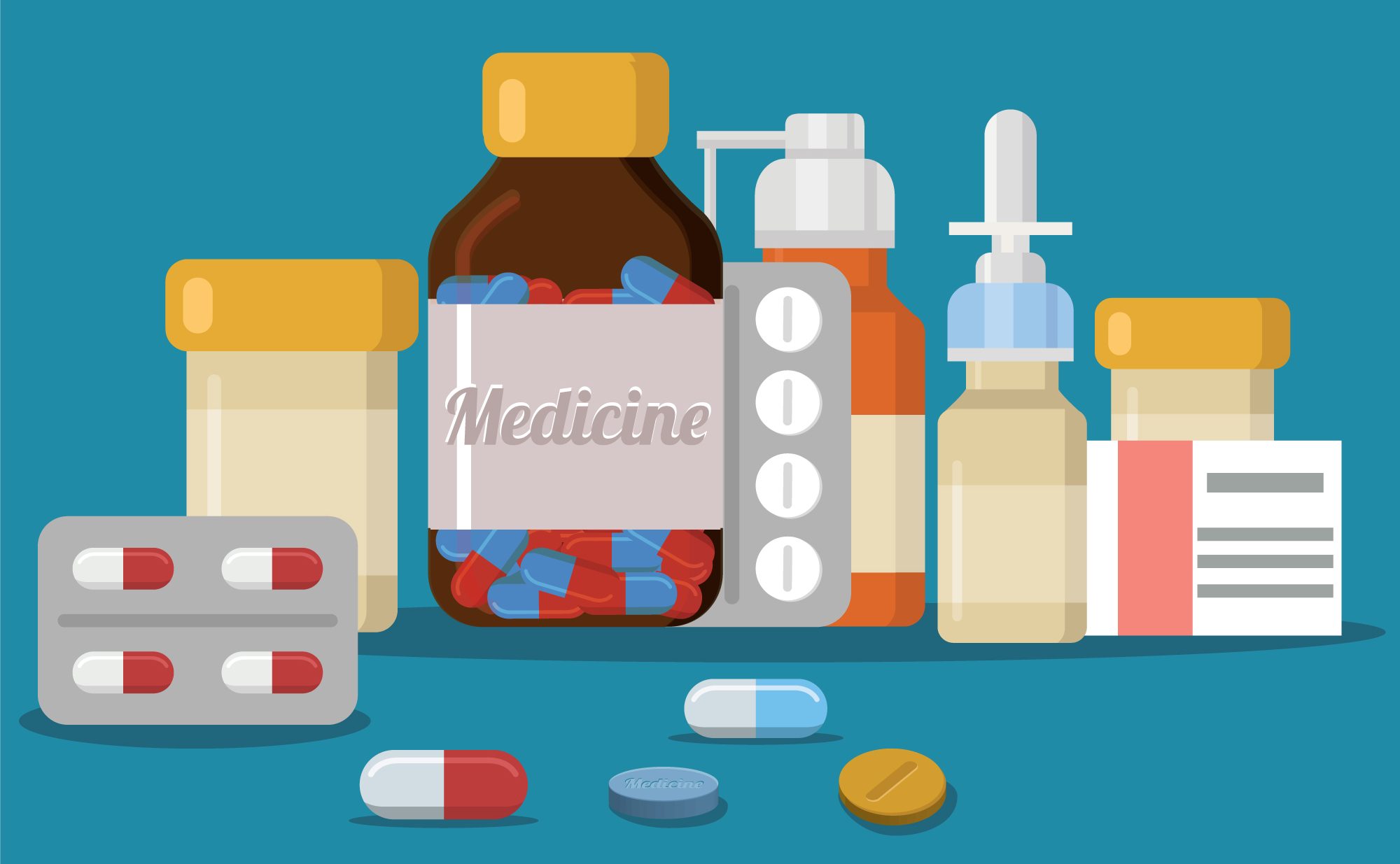
調剤というのは、薬剤師だけがおこなうことのできる「独占業務」です。
その意味について、まずは法律で定められた『調剤』についてみていこう!
調剤の定義は、実は裁判できめられた!?
医薬品医療機器等法(以下、薬機法と略しますっ!)や、薬剤師法など、薬局や薬剤師に関連する法律の隅からすみまで読んでも、『調剤=●●である』という記載は、実は無い。
で、どこで調剤の定義が法律的に決められたかというと、大正6年3月19日に大審院(今の最高裁判所)の判例(裁判所が示した法律的な判断のこと)に、こんな原文がある(↓)
(判例の原文)
「一定ノ処方ニ従ヒテ一種以上ノ薬品ヲ配合シ若クハ一種ノ薬品ヲ使用シテ特定ノ分量ニ従ヒ特定ノ用途ニ適合スル如ク特定人ノ特定ノ疾病ニ対スル薬剤ヲ調製スルコト」
・・・・カタカナで書かれると、そっと読み飛ばしたくなるよね(汗) なので、カタカナをひらがなに変換しつつ読みやすいように整えると、(↓)
(翻訳)
「一定の処方に従って一種以上の薬品を配合もしくは一種の薬品を使用して特定の分量に従い特定の用途に適合する如く特定人の特定の疾病に対する薬剤を調製すること」
要は『処方にしたがい薬を調整すること』と書いてあるんですね。この裁判で『調剤=薬の調整』という定義が初めて法律的に定義されたのですな。これが、狭義の意味での調剤にあたる。
薬機法・薬剤師法に書かれている調剤とは?
薬機法と薬剤師法、それぞれに対する施行令・施行規則の計6種類すべてに対して、『調剤』と書かれている部分を全部しらべた。
(※「薬機法とか施行令、施行規則の違いって何?」というあなたはこちらの記事でまとめてます→知らないでは済まない!薬機法(法律)・施行令・施行規則・通知の違い)
調べかたはシンプルに、各法令で「Ctrl+F(ページ内の検索)」をして『調剤』がヒットする条文を全て読んでいった。6種類の法令すべての『調剤』と書かれた文字をカウントすると、実に138回もあらわれ、途中で心が折れかけた。
ちなみに法令は「e-Gov 電子政府の総合窓口」の検索まどに、「医薬品」や「薬剤師」と検索すると、薬局や薬剤師に必要な法令が一覧で確認できるので便利。
以下に、しらべた条文をご紹介していこうと思う(調剤が目立つよう、赤字にする)。『調剤=薬の調整』として読んでもらうとしっくりくるので、ぜひ頭に思い浮かべながら読んでみてほしい。
【薬機法】(調剤された薬剤の販売に従事する者)第九条の二 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。
【薬機法施行規則】
(薬局における調剤)
第十一条の八 薬局開設者は、その薬局で調剤に従事する薬剤師でない者に販売又は授与の目的で調剤させてはならない。ただし、高度な無菌製剤処理を行うことができる作業室(以下「無菌調剤室」という。)を有する薬局の薬局開設者が、無菌調剤室を有しない薬局の薬局開設者から依頼を受けて、当該無菌調剤室を有しない薬局で調剤に従事する薬剤師に、当該無菌調剤室を利用した無菌製剤処理を行わせるときは、この限りでない。2 前項ただし書の場合においては、当該無菌調剤室を有しない薬局の薬局開設者は、当該無菌調剤室を有しない薬局で調剤に従事する薬剤師の行う無菌製剤処理の業務に係る適正な管理を確保するため、事前に、当該無菌調剤室を有する薬局の薬局開設者の協力を得て、指針の策定、当該薬剤師に対する研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。
第十一条の九 薬局開設者は、医師、歯科医師又は獣医師の処方箋によらない場合には、その薬局で調剤に従事する薬剤師に販売又は授与の目的で調剤させてはならない。
2 薬局開設者は、処方箋に記載された医薬品につき、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除き、その薬局で調剤に従事する薬剤師にこれを変更して調剤させてはならない。
第十一条の十 薬局開設者は、その薬局で調剤に従事する薬剤師が処方箋中に疑わしい点があると認める場合には、その薬局で調剤に従事する薬剤師をして、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤させてはならない。
第十一条の十一 薬局開設者は、調剤の求めがあつた場合には、その薬局で調剤に従事する薬剤師にその薬局で調剤させなければならない。ただし、正当な理由がある場合には、この限りでない。
ここで、薬機法施行規則の第十一条の十(青字にした条文)の内容に注目してもらいたい。書いてある内容をかんたんに言うと、「処方内容をが疑わしければ、疑義紹介してから調剤しなさい」ってことだ。
これは、処方監査と調剤(薬の調整)を分けているからこその記載と言える。
しかし!
いっぽうで、こんな条文も存在するのだ(↓)
【薬剤師法施行規則】
(居宅等において行うことのできる調剤の業務)
第十三条の二 法第二十二条に規定する厚生労働省令で定める調剤の業務は、次に掲げるものとする。一 薬剤師が、処方せん中に疑わしい点があるかどうかを確認する業務及び処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめる業務
二 薬剤師が、処方せんを交付した医師又は歯科医師の同意を得て、当該処方せんに記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務(調剤された薬剤の全部若しくは一部が不潔になり、若しくは変質若しくは変敗するおそれ、調剤された薬剤に異物が混入し、若しくは付着するおそれ又は調剤された薬剤が病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されるおそれがない場合に限る。)
これ、患者宅でおこなうことができる調剤行為についての条文ですが、、、冒頭に「調剤の業務は次に掲げるものとする」と書いてあり、調剤の業務として書かれている内容に「処方監査(青字部分)」が含まれるとしているじゃあーりませんか。
もうね、どう解釈したらよいか迷うよね。
このように、薬機法や薬剤師法からすると調剤の定義がイマイチなんとも定義がムズカシイ。。。
なので、最初に紹介した裁判の判例である『調剤=薬の調整』が法律の観点からみた定義と考えられる。
調剤って調剤事務がおこなっても良いの?
NO!ダメゼッタイ!法令によりNG!
『調剤=薬の調整』が裁判で定められた定義でしたよね。この調整という意味を調べると(↓)
調整:ある基準に合わせて正しく整えること
このように説明されている。この説明の「ある基準=処方せん」と置き換えて先ほどの調剤の定義にあてはめてみると、、、
『調剤=処方せんに合わせて薬を正しく整えること』
ピッキングというのは、処方せんに記載された薬を集める行為なので、ようは正しく整えることになる。最初にちらっと書いたけど、調剤とは薬剤師のみ行える行為(独占業務)なので、薬剤師以外はNG。薬を拾うだけでもダメなんですね。
ただ、係数確認(数の確認)であれば違反ではない。係数確認とはなんぞや?というと、薬剤師がピッキングした薬を処方箋と照らし合わせ、薬の名前と数があっているかチェックすること。
「ん?それ、監査じゃね?」と思った人もいるかもしれませんが、違います。『監査』とは、処方せんと一致しているかの確認だけでなく、飲み合わせなどの薬学的な判断も含まれる行為をさす。
あくまで処方せんと薬の実物が同じなかどうかの確認でしかないので、問題ない(関東厚生局の集団指導で確認済み)
ということで、ピッキングは調剤事務さんNGなので、薬の数や名前の確認をお願いしましょう。その他の調剤事務の仕事内容を知りたいひとは、「調剤薬局事務が未経験の人へ仕事内容、給料とか全部教える」でまとめてます。
ちなみに、海外では『テクニシャン』といわれる資格者が、一部の調剤行為(ピッキングなど)を手伝うことが認められている。
この制度、ほんと日本にも欲しいよね。。。。
国が薬局に求める業務から考える『調剤』の定義とは?


続いて、国が薬剤師(薬局)に求める業務内容から、調剤の定義を見ていこう。
薬局の仕事は対物業務から対人業務へ
医薬分業がはじまったころは、それこそ処方せん通りに薬を調整するだけが薬局の仕事だった。
しかし、「それ、薬剤師じゃなくて、機械じゃね?」ってことで、付加価値をだすために処方の監査だとか服薬指導、薬学的観点からの処方提案、なども薬剤師の重要な仕事として加わっていた。
さらに最近の薬局のおかみ(厚生労働省)は、「対物業務から対人業務に移行せいや!」と、やたらと声を大にしている。
なんじゃそりゃ?という人のために簡単に説明すると、処方せん通りに薬を拾って薬を渡すこと(物が中心の仕事=対物業務)は本来のしごとではなく、患者さんにメリットを出すこと(人が中心の仕事=対人業務)を頑張れ!とプレッシャーエールを送ってくれているのだ。
言い換えると、法律で決めた薬の調整だけ(=対物業務)だけでは足りないから、患者さんに対してもっと有益な仕事(=対人業務)をしましょうね、ということ。
法律では『調剤=薬の調整』だけであったが、こういった薬剤師の業務に価値を出そうとしてきた背景と、厚労省からの要望がからみあい、薬剤師のメインの仕事である『調剤』の意味にどんどん厚みが増えてしまった。
薬剤師に求められる仕事内容から導かれる調剤の定義とは?
対人業務を充実させるため、いまの薬剤師に求められている調剤とは、下記のような業務をさす。
- 処方監査
- 疑義紹介
- 薬の調整
- 調整後の薬剤の監査
- 後発品の提案
- 服薬指導
- 医薬品の交付
- 薬歴簿の記録
- 服用後の経過観察
- 医薬品の適切な管理
- 最新情報の収集
ようは、患者さんに価値をだす作業すべてのことです。 薬局薬剤師のかたなら、すでに取り組まれているようなことですね。
これら全部を含めて『調剤』とするのが広義の意味での調剤です。
まとめ
さいごに改めて、調剤の定義をまとめると(↓)
<狭い意味=法律で決められた>
薬の調整。医師の処方せん通りに医薬品をそろえること。
<広い意味=薬剤師の業務内容から決められた>
医師の処方内容が薬学的に正しいのか判断(処方監査)し、相互作用のチェック、患者への服薬指導とその内容の記録・管理、後発医薬品の選択など、医薬品に関わる多種多様な業務すべて。
薬剤師に求められる業務内容が昔にくらべるととんでもなく増えているので、いずれ法律上の調剤の定義が変わるかもしれません。
それまでは、上記2つの意味を状況によって使い分けて貰えば対応できるので、ぜひ覚えておきましょう!
薬局に関する情報収集に便利なサイト
最後に、私がブログを書くときの記事ネタを探したり、情報収集に活用しているサイトの『m3
m3は、薬局に関連性のある最新情報を国内外問わずにまとめて確認できるため、効率的に知識を補えるので助かっている。
一例ですけど、こういった情報が毎日更新される↓


こう、非常に興味をひかれるコンテンツが豊富。それで、毎日更新される。 なので、毎朝の通勤時間でサッと記事のタイトルだけ見ておけば、「え、知らないの?」といった取り残されるリスクが無くなる。※アプリがあるので便利。
閲覧するためには登録が必要なんだけど、お財布にやさしく登録費が無料。登録時に入力する内容は名前とか生年月日などで、「1分」あれば登録ができる。
なので、登録するか悩むぐらいなら、その悩んでる時間で登録完了する。
あと地味に嬉しいのは、サイト内の勉強動画を見ると『m3ポイント』なるものが貯まり、『Amazonギフト』と交換できる。情報収集しながらお小遣い稼ぎできるのが一石二鳥。
他の薬剤師向け情報サイトでは有料登録しないと読めないネタが、m3で掲載してることもあるので、登録して損は無いというか、「使わないのが損」な貴重なサイト。
すべての薬剤師に自信を持っておススメできるので、他の薬剤師に差をつけられる前にぜひ活用してみてください(و`ω´)و
公式サイトm3
【答え】継続的な勉強
2019年5月に厚労省が出した薬剤師の需要と供給についてのレポートをご存知ですか?
これ簡単に言うと『すでに薬剤師が余り出している』という内容が書いてある。需要を上回る数の薬剤師がいるそうだ。
突然ですが、最近の新卒の採用事情はご存知ですか?
調剤薬局やドラッグストアは、昔はそれこそ薬剤師の資格を持っていれば即採用というぐらい簡単でした。
でも今はちがう。優秀な成績の薬剤師に絞り始めていて、成績が悪い薬剤師は採用しない。
この流れが、じわじわと中途採用にも来ています。なぜそんなこと分かるかというと、これでも薬剤師の採用を担当してますから、動向はチェックしてるのです。
薬剤師が飽和していく未来に対し、すこしでも質を高めて需要の高い人材となるため、ぜひ日々の勉強に役立ててください(و`ω´)و