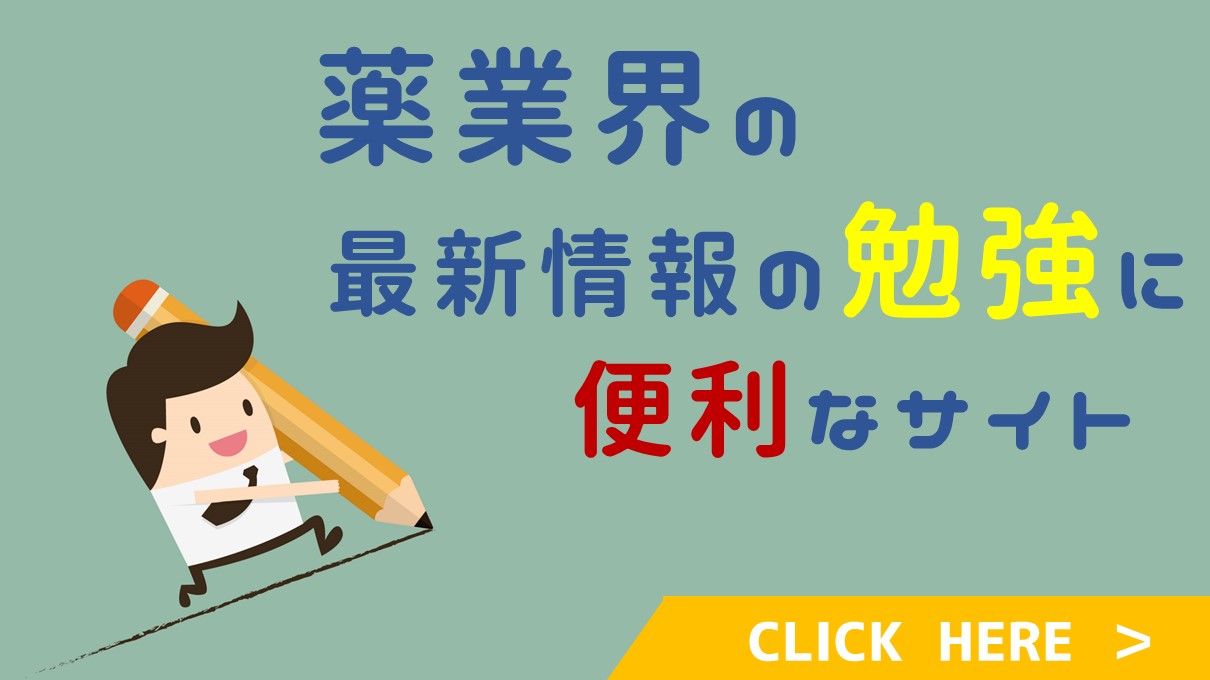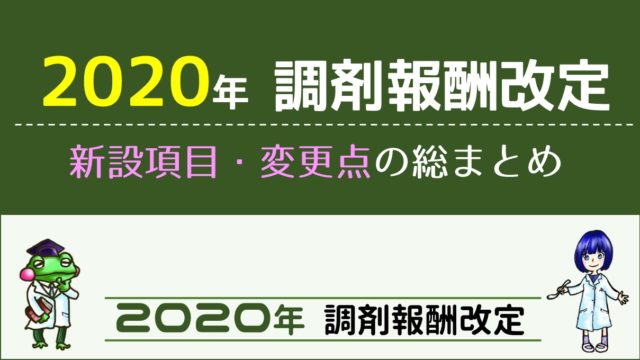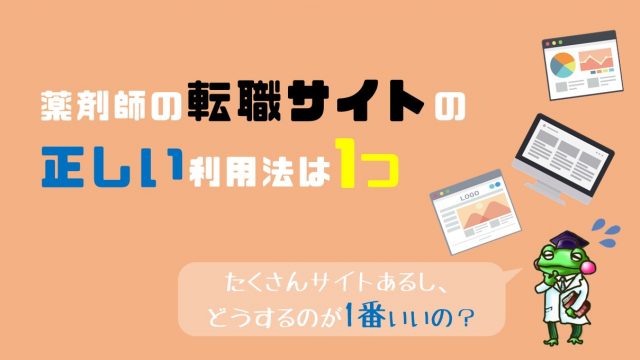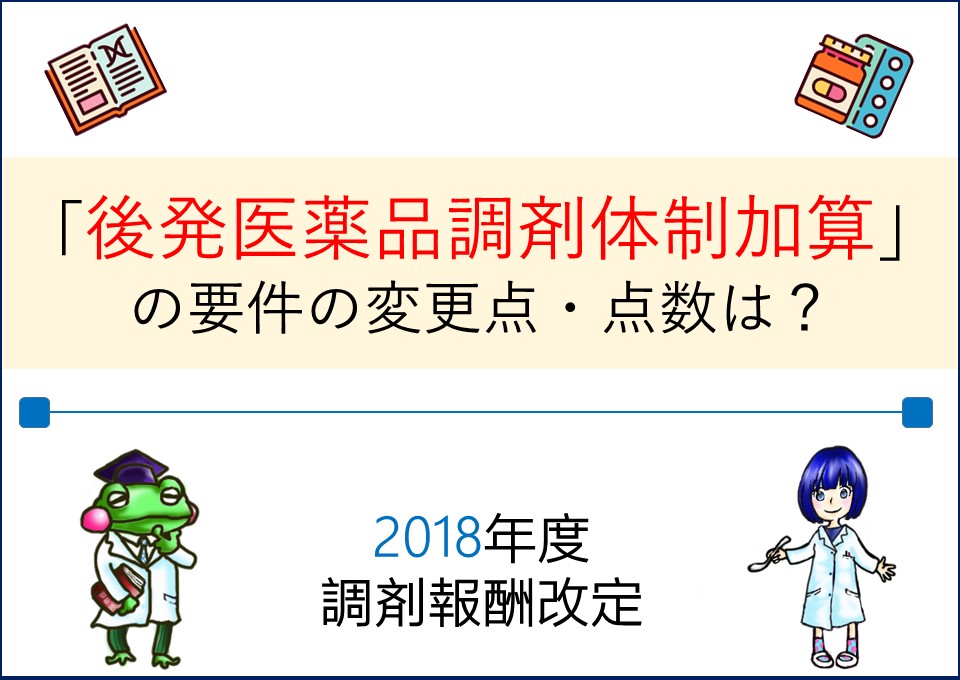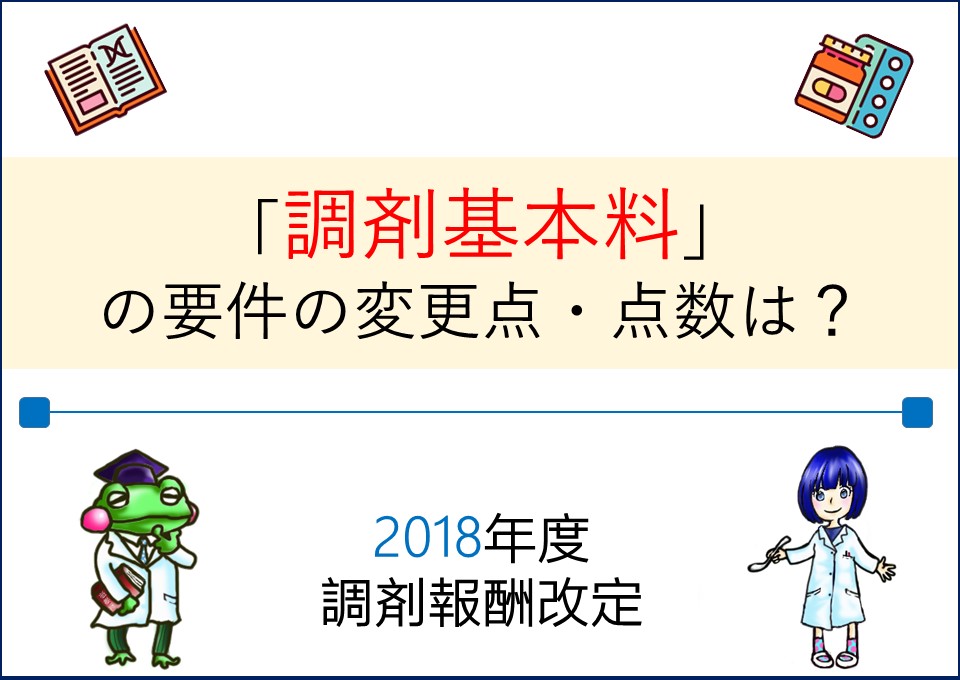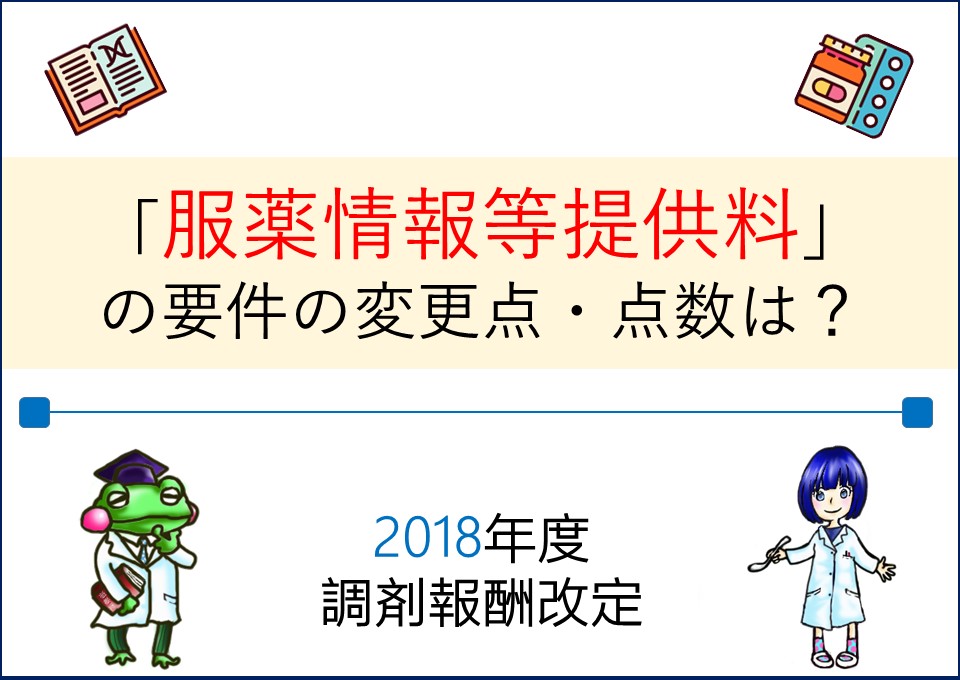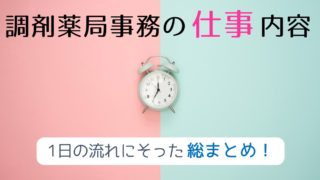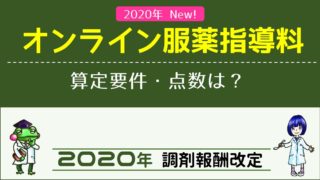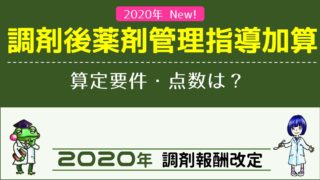『後発医薬品調剤体制加算』は、それまで2区分であったのに対し、2018年度から3区分へと増える。さらに後発品の割合が低い場合には減算規定が設定されることになった。
3区分になることは予想していなかったけれど、減算規定に関しては噂としては出ていたので、「あぁ、とうとう厚労省が本気を出してきたか」という印象ですね。
これで、いままでは「うちの薬局は、門前の先生が先発しか処方しないからな~!」と後発加算を無視していた薬局も、後発品の割合が低いと減算になるってことで、後発品の割合を増やすために努力しなければならない。
まずは、算定要件である後発品の仕様割合や点数、減算されるのは後発品が何割からなのか、といった変更点を押さえて、焦らず対処してきましょう!
後発医薬品調剤体制加算の点数、後発品の割合は?
【変更前】
後発医薬品調剤体制加算1 65%以上:18点
後発医薬品調剤体制加算2 75%以上:22点
【変更後】
後発医薬品調剤体制加算1 75%以上:18点
後発医薬品調剤体制加算2 80%以上:22点
後発医薬品調剤体制加算3 85%以上:26点(新設)
減算規定:後発品割合が20%以下 2点減点(新設)
今までは2区分であったのに対し、2018年度から3区分に増える。
これは、厚生労働省が『後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ(H25年4月)』で「平成30年度から平成32年度末までの間のなるべく早い時期に80%以上とする」と目標を掲げているのが理由と考えられる。
目標達成のために80%を中心とした後発品割合を設定して、全ての薬局を平均したら80%が達成できているというストーリーを作りたいのだろう。
減算規定の要件は?
[調剤基本料]
注6 後発医薬品の調剤に関して、別に厚生労働大臣が定める薬局において調剤した場合には、所定点数から2点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
(「別に厚生労働大臣が定める」の条件が次↓)
[施設基準]
調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が2割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
(2) (1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。
後発加算を算定するための後発品割合の変更内容を見て貰った通り、後発品加算を算定するための後発割合ハードルが高くなってしまっている。
そうすると、「うちの薬局で達成するのなんて無理、無理!もう、後発品とかどうでも良いわ!」という薬局で出てくる。
逃がしませんよ!(※フリーザの声)
ということで、今回から減算規定が加わる。 要件を簡単にまとめると『20%以下なら2点を減算しますよ!ただし、1月の処方せんが600回を超えない場合ね!』という内容ですね。
1月の処方箋が600回を超えない場合は、売り上げを試算すると経営的にギリギリなのラインなので、減算対象から外したのかなー。
ちなみに、毎月1,000回の処方箋を応需している薬局で後発品の減算をくらうと、2万円の減額になる。
・・・ん?あれ?この程度の減額なら、無理に後発品へ変えず、先発品のままで薬価差益取った方が利益出そうな気がしてきたぞ!?
この辺りは、自分の薬局での納入価と相談して、減算を避けた方が得なのか、あえて先発で調剤を続けた方が得なのか、しっかり計算した方が良さそう。うちの薬局も計算しよーっと。
後発医薬品調剤体制加算を取るためには?
やっぱり減算を避けたい、後発加算を取りたい人向けに、「どうやったら後発品の割合を増やすことができるのか?」という方法を伝えたい。 これはすごくシンプルで、以下の2点を実践するのみ。
- 処方医に後発品へ切り替えて貰うよう交渉する。
- 患者に根気よく伝える。
1番手っ取り早く、かつ、影響度が大きいのは、やっぱり医師に直接交渉することですね。
「どうやって交渉するの!?」という困っているあなたに向けて、プジキが交渉するときの手順を教えましょう。
- 交渉したい病院から処方される薬の中で、後発品が存在していて使用数量が多い薬を上位10個ぐらい調べる。
- その中で、先生が気にしなそうな薬(専門の資料科目以外の薬が狙い目)をピックアップ。
- ピックアップした薬を後発に変えたい旨を、先生の顔色をうかがいながら、正直な理由(後発加算が取れないと経営が苦しいんです。。)と共に伝える
- 後発の銘柄指定ではなく、一般名で処方して貰うように伝える。
交渉する薬に関しては、『この薬の●割を後発品に変えることができれば、全体の後発割合が■%になる。こちらの薬の場合は▲割変えればOK』といったところまでシミュレーションしてから、医師との交渉に臨むようにしましょう。
このシミュレーションができていないと、交渉の場で先生に断られた際の代替案が提案できなくなり、テンパって終了になりかねないですからね。。。
あと、2018年度から病院側の処方箋料にある一般名処方加算も高くなるので、そのことをアピールしつつ一般名処方でお願いしてあげると喜ばれるはず。
【変更前】
[処方箋料]
イ 一般名処方加算1 3点
ロ 一般名処方加算2 2点
【変更後】
[処方箋料]
イ 一般名処方加算1 6点
ロ 一般名処方加算2 4点
あと、後発品の割合を増やす方法としては、患者さんへの地道な布教活動を続けることですね。 これはもう、一人ずつお伝えして、後発に変えていくだけ。 千里の道も一歩から。
・・・偉そうに語りましたけど、これから先生たちとの交渉(自分が担当してるのは全店舗の半分ぐらい。。)が始まると思うと憂鬱になったので、これから自分が踏ん張れるように励ましの意味も込めて書きました(汗
この記事を読んでくれた皆さん、後発加算の算定に向けて、一緒に(辛い交渉とか)頑張りましょう!
[参考]2018年の調剤報酬改定内容の全体を確認したい方は、こちらの記事にまとめてあります。
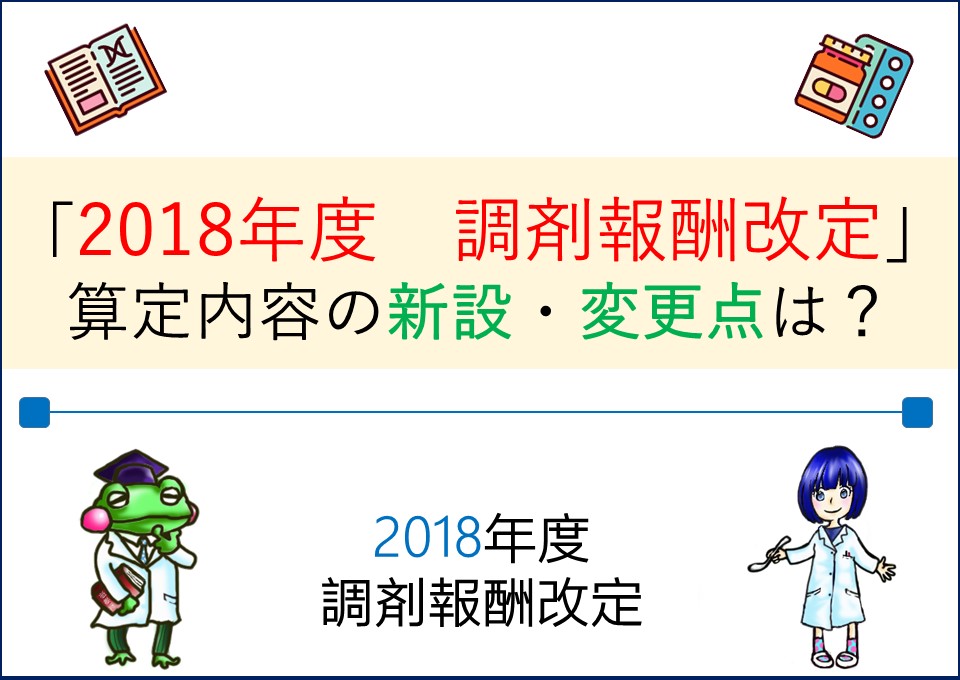
薬局に関する勉強に便利なサイト
最後に、私がブログを書くときの記事ネタを探したり、情報収集に活用しているサイトの『m3』をちょっとだけご紹介。
m3は、薬局に関連性のある最新情報を国内外問わずにまとめて確認できるため、効率的に知識を補えるので助かっている。
一例ですけど、こういった情報が毎日更新される↓

こう、非常に興味をひかれるコンテンツが豊富。それで、毎日更新される。 なので、毎朝の通勤時間でサッと記事のタイトルだけ見ておけば、「え、知らないの?」といった取り残されるリスクが無くなる。※アプリがあるので便利。
閲覧するためには登録が必要なんだけど、お財布にやさしく登録費が無料。登録時に入力する内容は名前とか生年月日などで、「1分」あれば登録ができる。
なので、登録するか悩むぐらいなら、その悩んでる時間で登録完了する。
あと地味に嬉しいのは、サイト内の勉強動画を見ると『m3ポイント』なるものが貯まり、『Amazonギフト』と交換できる。情報収集しながらお小遣い稼ぎできるのが一石二鳥。
他の薬剤師向け情報サイトでは有料登録しないと読めないネタが、m3で掲載してることもあるので、登録して損は無いというか、「使わないのが損」な貴重なサイト。
すべての薬剤師に自信を持っておススメできるので、他の薬剤師に差をつけられる前にぜひ活用してみてください(و`ω´)و
公式サイトm3
【答え】継続的な勉強
2019年5月に厚労省が出した薬剤師の需要と供給についてのレポートをご存知ですか?
これ簡単に言うと『すでに薬剤師が余り出している』という内容が書いてある。需要を上回る数の薬剤師がいるそうだ。
突然ですが、最近の新卒の採用事情はご存知ですか?
調剤薬局やドラッグストアは、昔はそれこそ薬剤師の資格を持っていれば即採用というぐらい簡単でした。
でも今はちがう。優秀な成績の薬剤師に絞り始めていて、成績が悪い薬剤師は採用しない。
この流れが、じわじわと中途採用にも来ています。なぜそんなこと分かるかというと、これでも薬剤師の採用を担当してますから、動向はチェックしてるのです。
薬剤師が飽和していく未来に対し、すこしでも質を高めて需要の高い人材となるため、ぜひ日々の勉強に役立ててください(و`ω´)و