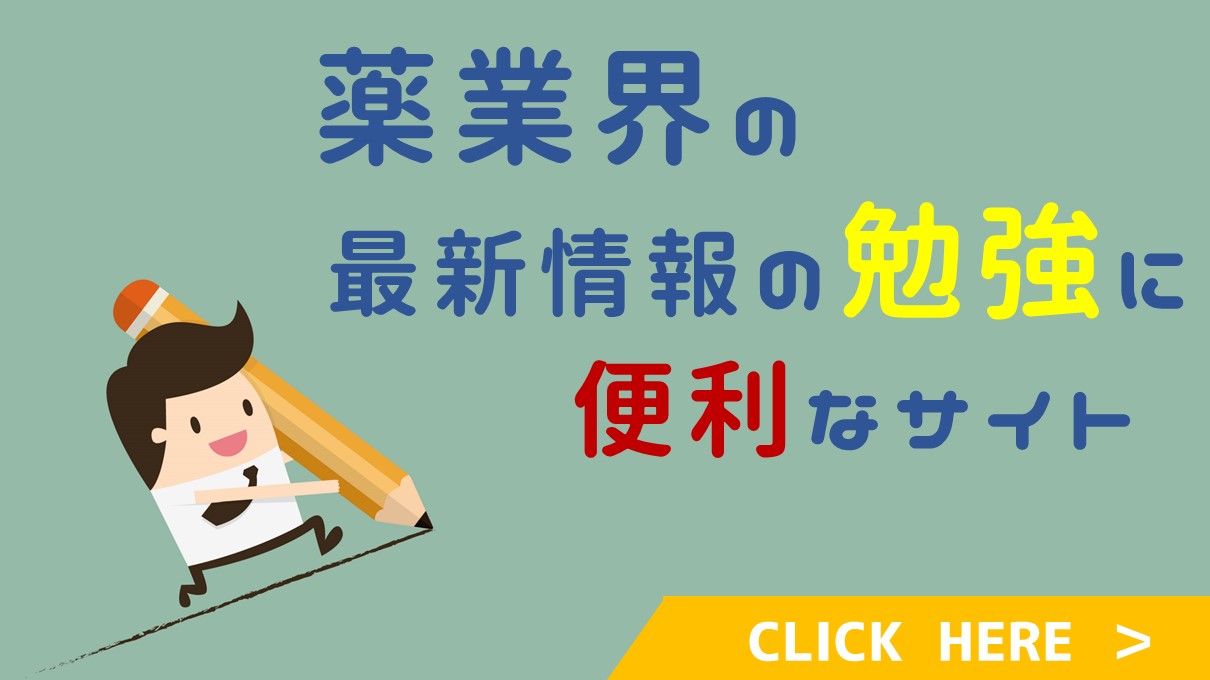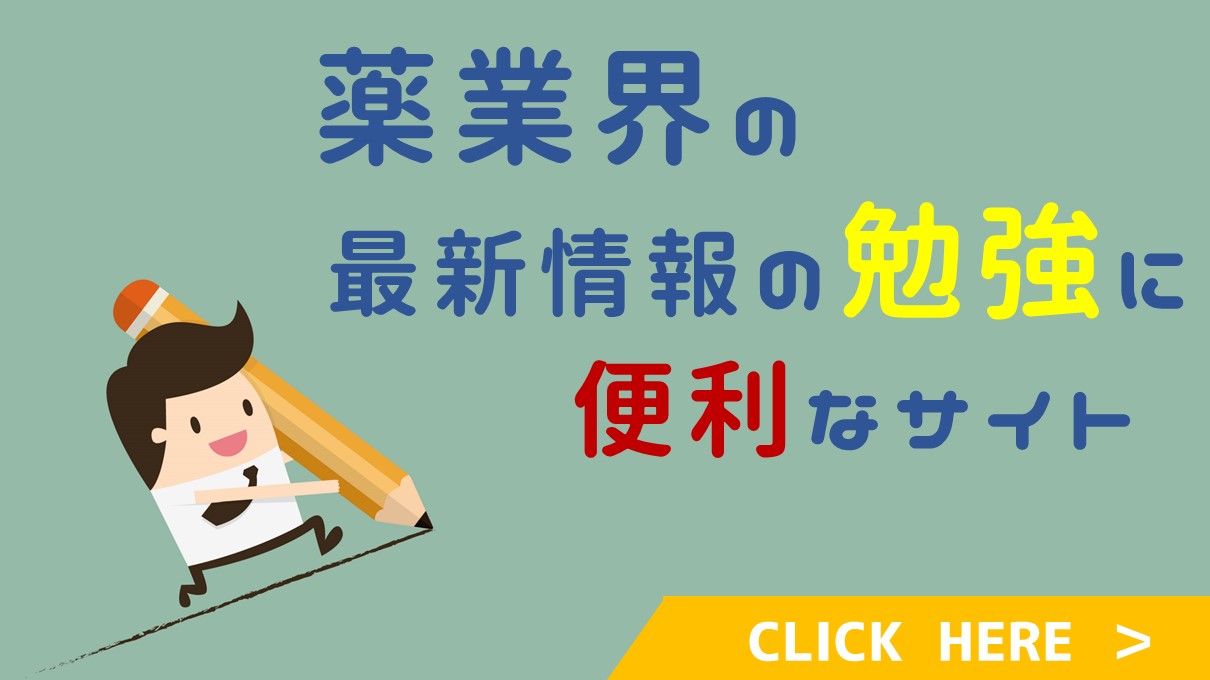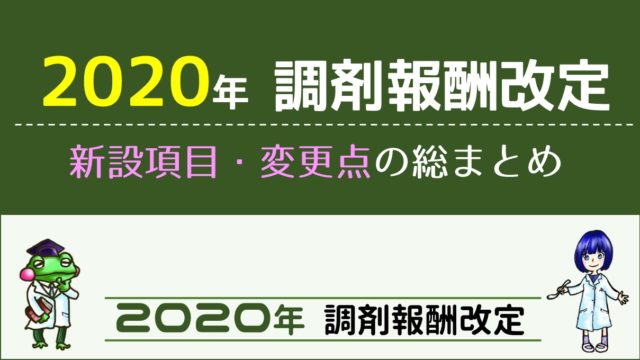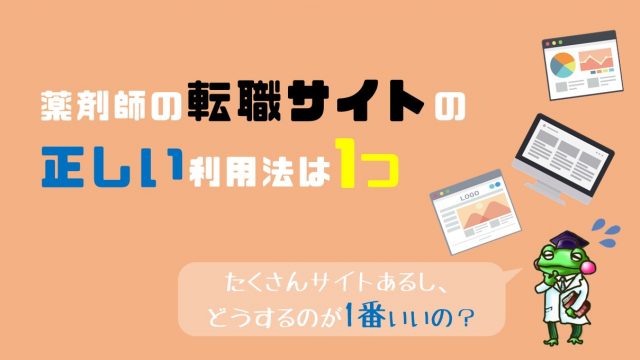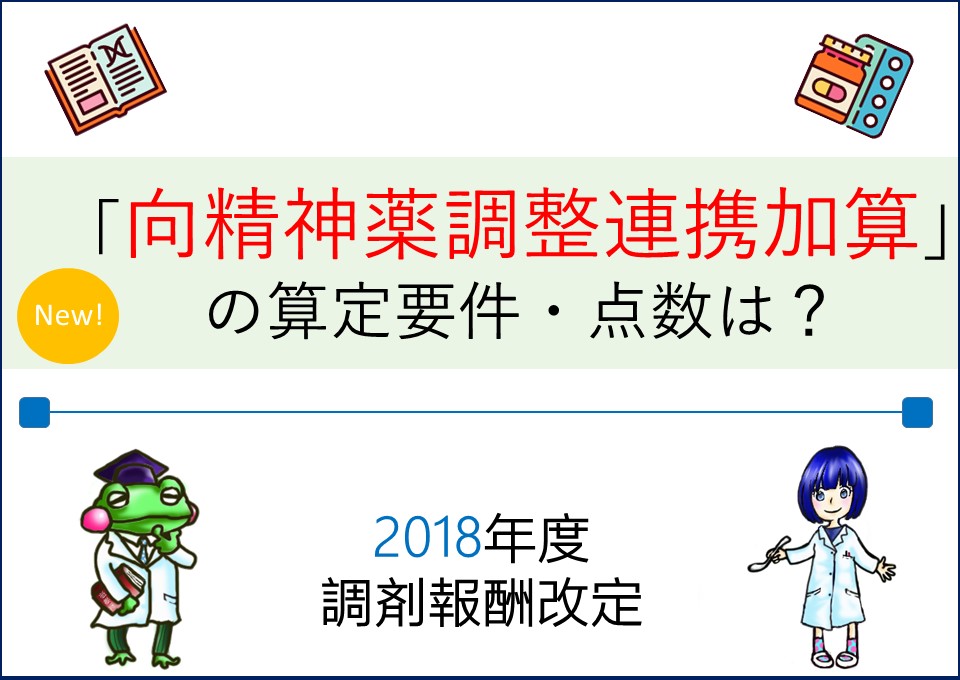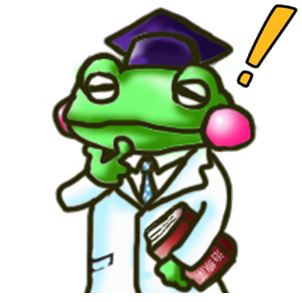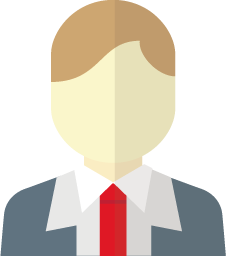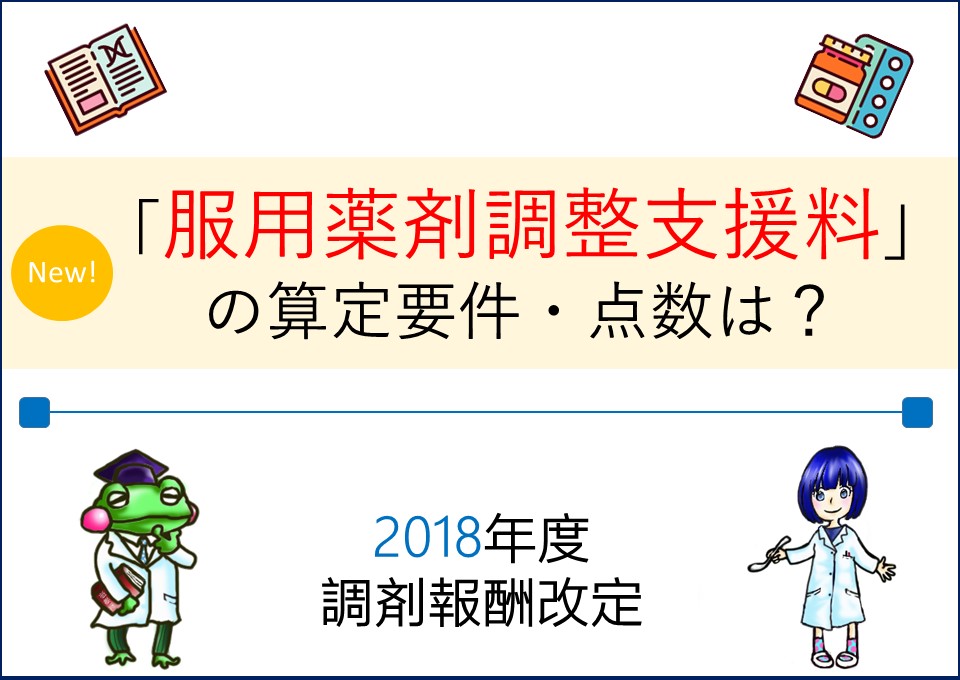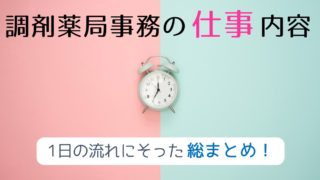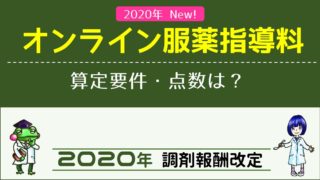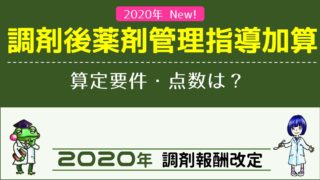これは、向精神薬の多剤処方やベンゾジアゼピン系の向精神薬の長期処方を適正化するために、病院側に新設された加算。
【処方料】向精神薬調整連携加算:12点(新設)
【処方せん料】向精神薬調整連携加算:12点(新設)
院内処方の場合は【処方料】として算定でき、処方せんを発行する場合は【処方せん料】として算定できるわけですな。
で、、、実はこの加算、、、算定要件に「薬剤師との連携」が含まれている。
この加算を上手く利用すれば、2018年より新設される『地域支援体制加算』に含まれるハードル高そうな算定要件の、『服用情報等提供料』を算定できそうと思ったので、読んでくれてるあなたにシェアします。
この記事を読んで「お、確かに使えそう!」と思ったら、ぜひ職場でシェアして前向きに取り組んで見て下され!
算定要件は?
直近の処方時に、向精神薬の多剤処方の状態にあった患者又はベンゾジアゼピン系の薬剤を12月以上、連続して同一の用法・用量で処方されていた患者であって、減薬の上、薬剤師(処方料については薬剤師又は看護職員)に症状の変化等の確認を指示した場合
加算が新設される背景は?
中医協様の個別改定項目の資料では、このように↓書いておられる。
向精神薬の多剤処方やベンゾジアゼピン系の抗不安薬等の長期処方の適正化推進のため、向精神薬を処方する場合の処方料及び処方せん料に係る要件を見直す。また、向精神薬の多剤処方等の状態にある患者に対し、医師が薬剤師と連携して減薬に取り組んだ場合の評価を新設する。
といった具合に、「医師と薬剤師が連携して向精神薬を減薬したら評価しますよ!」と言って下さっている。
これは、薬剤師の評価を上げるための土台を国が整備してくれたと、前向きに解釈している。
これ、服薬情報等提供料と相性よくね?
2018年度から新設された『地域支援体制加算』で、調剤基本料1以外の薬局に求められる難易度の高い要件の中に、『服薬情報等提供料』という項目がある。
※『地域支援体制加算』に関してはコチラ↓の記事でまとめてるので、算定要件が分からない人は併せてチェックしてみてください。
関連記事『地域支援体制加算』とは?点数や算定内容・ポイントは?
この服薬情報等提供料は昔からある薬学的管理料なんだけど、算定したことある人の方が少ないと思うので簡単に説明すると↓
〇『服薬情報等提供料』とは?
薬が適切に使用されているか把握し、患者の同意を得て、患者へ情報提供するか医療機関に文書で情報提供を行った場合に、月1回だけ算定できる。
という、加算である。 これ、、、算定したことある薬局、どれだけあるの(汗 自分はお恥ずかしながら、経験したことない。
で、ですよ。
向精神薬調整連携加算の算定要件を見ると、「薬剤師に症状の変化等を確認した場合」と書いてあるじゃない。
え、聞こえないって?
「薬剤師に症状の変化等を確認した場合」と書いてあるじゃなーい!!
そう、向精神薬調整連携加算を算定するためには、薬剤師に症状の変化を確認しなければ算定できないのだ。
なので、門前の医師にこんな(↓)提案をして、病院では『向精神薬調整連携加算』を算定して、薬局では『服薬情報等提供料』を取り、さらには『地域支援体制加算』まで狙えるのではないか。
このように、算定できそうな患者さんを何人かピックアップしておき、病院(医師)に向精神薬調整連携加算の提案をしつつ、シレっと服薬情報等提供料の要件を満たすことが可能だ。
・・・ん?こんな提案を医者にできないって?
提案するんですよ!生き残るために!
薬局の薬剤師も、生き残るために医師に対して営業活動を行うべき。 コミュニケーションを定期的に取って、何かあったときに提案できる関係性を構築することは非常に大事だ。
もし、そういった関係性を築けていないのであれば、上記の提案をネタに、ぜひ先生に提案してもらいたい。 医者も人間なんだから、算定が取れて収入が増えることは嬉しいので、きっと話は聞いてくれる。
それに、薬を減らすことができるのは、患者さんには良いことでしかないので、医療者の立場としてもぜひ積極的に動いてもらいたい。
もし、話を聞き入れない医者だったとしたら、「こいつは変なヤツ」と割り切って無視すればよいだけ。 ドライに考えましょう。
まとめ
病院向けに新設された『向精神薬調整連携加算』だけど、考え方しだいでは薬局の加算とも関連性が強い。
減薬は患者さんにとって間違いなく良いことなので、先生に減薬を提案して実現し、そして上手いこと加算も取れるよう、、一緒に頑張りましょう!!
[参考]2018年の調剤報酬改定内容の全体を確認したい方は、こちらの記事にまとめてあります。
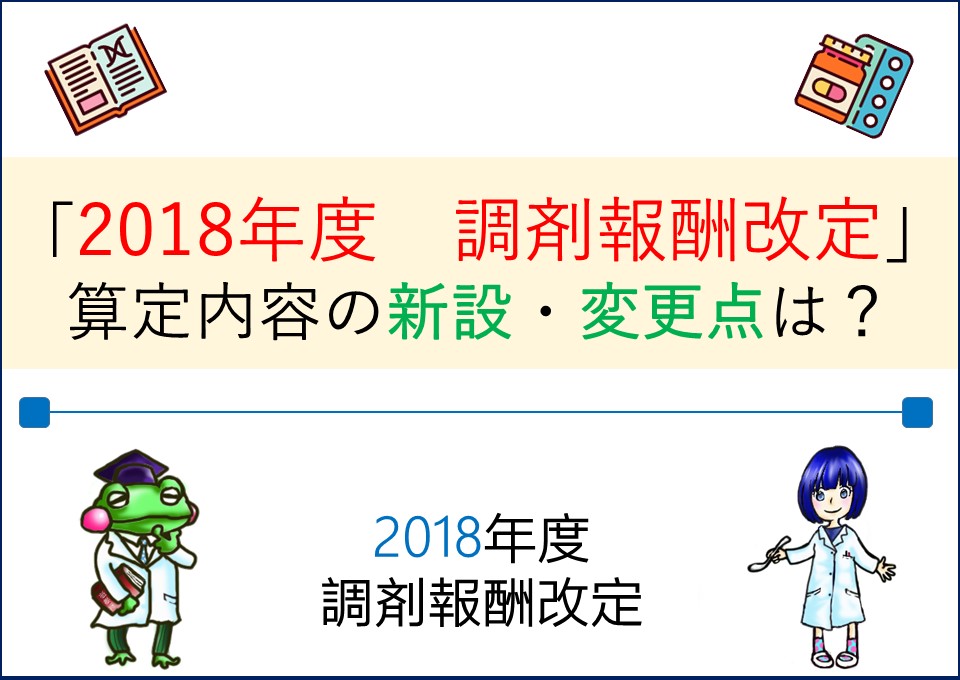
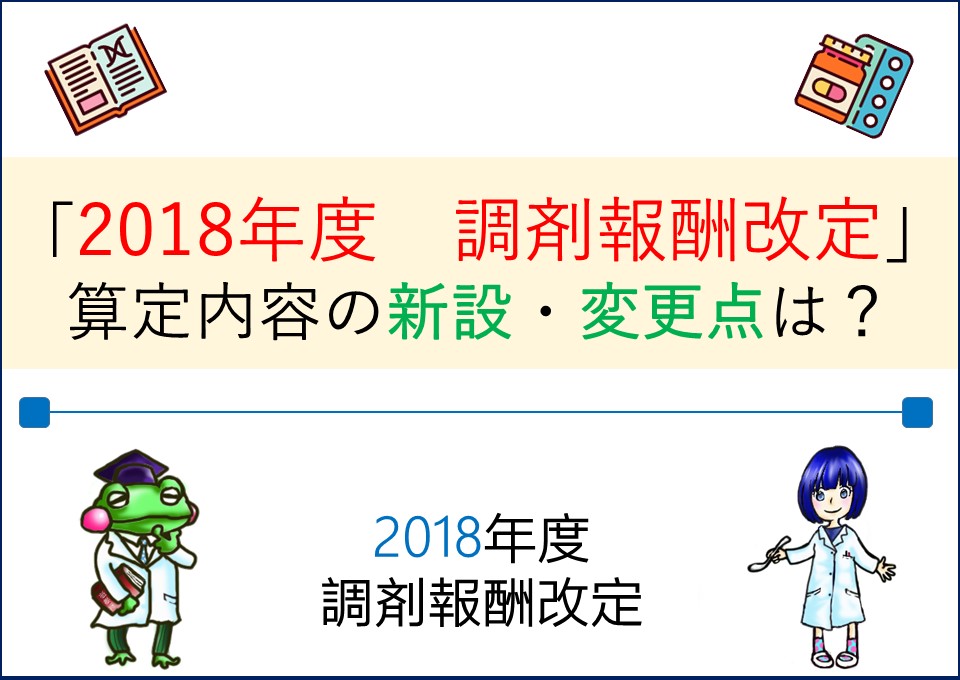
薬局に関する勉強に便利なサイト
最後に、私がブログを書くときの記事ネタを探したり、情報収集に活用しているサイトの『m3
m3は、薬局に関連性のある最新情報を国内外問わずにまとめて確認できるため、効率的に知識を補えるので助かっている。
一例ですけど、こういった情報が毎日更新される↓


こう、非常に興味をひかれるコンテンツが豊富。それで、毎日更新される。 なので、毎朝の通勤時間でサッと記事のタイトルだけ見ておけば、「え、知らないの?」といった取り残されるリスクが無くなる。※アプリがあるので便利。
閲覧するためには登録が必要なんだけど、お財布にやさしく登録費が無料。登録時に入力する内容は名前とか生年月日などで、「1分」あれば登録ができる。
なので、登録するか悩むぐらいなら、その悩んでる時間で登録完了する。
あと地味に嬉しいのは、サイト内の勉強動画を見ると『m3ポイント』なるものが貯まり、『Amazonギフト』と交換できる。情報収集しながらお小遣い稼ぎできるのが一石二鳥。
他の薬剤師向け情報サイトでは有料登録しないと読めないネタが、m3で掲載してることもあるので、登録して損は無いというか、「使わないのが損」な貴重なサイト。
すべての薬剤師に自信を持っておススメできるので、他の薬剤師に差をつけられる前にぜひ活用してみてください(و`ω´)و
公式サイトm3
【答え】継続的な勉強
2019年5月に厚労省が出した薬剤師の需要と供給についてのレポートをご存知ですか?
これ簡単に言うと『すでに薬剤師が余り出している』という内容が書いてある。需要を上回る数の薬剤師がいるそうだ。
突然ですが、最近の新卒の採用事情はご存知ですか?
調剤薬局やドラッグストアは、昔はそれこそ薬剤師の資格を持っていれば即採用というぐらい簡単でした。
でも今はちがう。優秀な成績の薬剤師に絞り始めていて、成績が悪い薬剤師は採用しない。
この流れが、じわじわと中途採用にも来ています。なぜそんなこと分かるかというと、これでも薬剤師の採用を担当してますから、動向はチェックしてるのです。
薬剤師が飽和していく未来に対し、すこしでも質を高めて需要の高い人材となるため、ぜひ日々の勉強に役立ててください(و`ω´)و